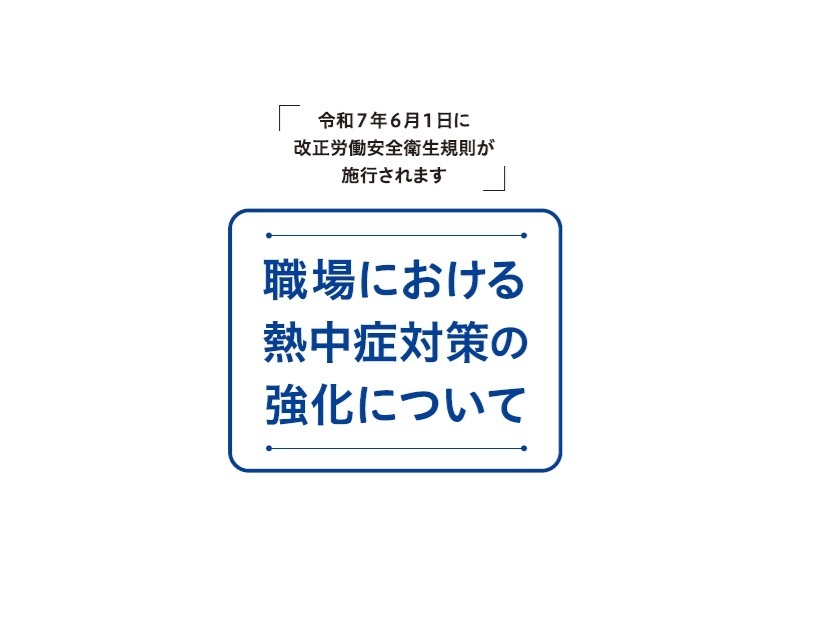新着情報・お知らせ
2025.11.20【労働法】労働基準監督署からの呼び出し!? 『出頭要求書』が届いた場合には
労働基準監督署は、企業を監督・調査する機関であり、労働者からの相談や申告、あるいは定期的な監督のなかで、なんらかの労働法違反の疑いがある場合に企業を調査します。
労働基準監督署の調査というと、突然の事業場への立ち入り調査をイメージしますが、最近では、事業場に立ち入らず、会社の責任者を呼び出して話を聞く形式の調査も増えています。
この呼び出しの際に、労働基準監督署から送られてくるのが「出頭要求書」です。
企業の代表者は特に理解しておきたい、出頭要求書が届いた際の適切な対処法や、出頭要求書を無視した場合のリスクなどについて解説します。
役割と出頭要求書が送付されるケース
労働基準監督署は、労働基準法や最低賃金法といった労働関係法令が企業で適切に守られているかを監督する厚生労働省の専門機関です。
その主な業務の一つに、企業への調査があります。
臨検監督には、事業場の業種や規模、過去の違反歴などを考慮して、計画的に実施される「定期監督」、労働者から申告があった場合に、その事実を確認するために実施される「申告監督」、そして、労働災害が発生した場合に、その原因究明と再発防止のために実施される「災害時監督」などがあります。
これらの監督は、労働基準監督官が事業場を訪問して行われることもあれば、会社の責任者を呼び出し、書類の確認や聞き取りといった方法で行われることもあります。
ちなみに、事業場を訪問する立ち入り調査のことを「臨検監督」と呼びます。
呼び出しは、労働基準監督署が臨検監督をせずとも、会社の代表者や労務担当者から直接話を聞くことで問題解決につながると判断した場合に実施されます。
その際に送付されるのが「出頭要求書」です。
出頭要求書が届くのは、主に3つのケースが考えられます。
一つ目は、在職中の従業員や退職した元従業員から、労働基準監督署に労働基準法違反に関する相談や申告があった場合です。
たとえば、残業代や休日出勤手当が支払われていない、法定労働時間を大幅に超えて働かされているなどの申告があった場合、労働基準監督署は出頭を求めて事実関係を確認しようとします。
二つ目は、臨検監督の際に必要な帳簿書類が揃っていなかったり、記載内容が不十分だったりした場合に、後日、不足している書類を持参するよう出頭を求められることがあります。
三つ目は、定期監督などの際に、軽微な違反が発見され、その場で是正勧告が行われたものの、その後の是正状況が確認できなかったため、あらためて状況を確認するために呼び出されることもあります。
出頭までに用意しておくべき書類
出頭要求書が届くと、多くの責任者は「何か重大な問題があるのだろうか」と不安になるかもしれません。
重要なのは、焦らずに通知書の内容を確認し、適切な準備をすることです。
出頭要求書には、呼び出し日時、出頭場所(労働基準監督署)、持参すべき書類などが記載されています。
まずはこれらの情報をしっかりと確認しましょう。
特に重要なのは、持参書類です。
賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書、就業規則など、用意する持参書類から、労働基準監督署が何を確認したいのかを読み取ることができます。
まずは速やかに社内の関係部署(経営陣、人事、経理など)に情報を共有し、通知書に記載された書類を集めましょう。
もし、不足している書類や不備がある書類があれば、労働基準監督署にその旨を伝え、いつまでに用意できるのか説明することが大切です。
同時に、関連する事実関係を調査します。
たとえば、特定の従業員からの申告が疑われる場合は、その従業員の労働時間や賃金支払い状況を詳しく確認しておく必要があります。
さらに、労働基準監督官の質問にどのように答えるかを事前に検討しておくことも大切です。
あいまいな回答や、虚偽の説明は、さらなる問題を引き起こす可能性があります。
事実に基づき、誠実かつ明確に回答する姿勢が求められます。
出頭要請を無視すると強制捜査に発展する?
もし、社内での対応がむずかしいようであれば、専門家に相談しましょう。
労働基準監督署の調査は、専門的な知識が要求される場合があります。
不安な場合は、弁護士や社会保険労務士といった労働法務の専門家へ相談することをおすすめします。
そして、一番やってはいけないことは、出頭要求書を無視することです。
労働基準監督署は、労働基準法に基づき、企業に報告や出頭を命じる権限を持っています。
出頭要求書を無視することは、この規定に違反することになります。
何より、出頭要求を無視すると、労働基準監督署に「この会社は何か隠しているのでは?」と疑念を抱かせることになります。
より厳しい対応、たとえば強制力のある臨検監督に移行する可能性が高まります。
強制捜査では、労働基準監督官が裁判所の交付した令状を持って、強制的に事業場に立ち入り、調査を行います。
強制捜査にまで発展してしまうと、企業の社会的信用は大きく損なわれ、事業活動にも深刻な影響が出る可能性があります。
労働基準監督署からの出頭要求は、会社の経営者や担当者にとってはプレッシャーのかかるものですが、「厄介な問題」ととらえるのではなく、企業の労働環境やコンプライアンス体制を見直すよい機会と考え、真摯に向き合うことが大切です。
2025.11.20【人的資源】『年功序列』が適している組織と適さない組織
日本企業では、成果主義やジョブ型雇用が主流となりつつあるとされてきました。
しかし、2025年に行われた民間の研究所の調査では、旧来の年功序列型の人事制度を望む声が、成果主義を上回る結果となりました。
これは、調査開始から36年で初めての逆転現象であり、働き手たちの価値観が多様化していることを示しています。
では、若い社員を中心に増えている年功序列を望む声に、企業としてどのように向き合えばよいのでしょうか。
年功序列が適している組織と適さない組織について、多角的な視点から考えます。
年功序列が広まった高度経済成長期
年功序列制度は、戦後の高度経済成長期に日本の多くの企業で導入され、広まっていきました。
終身雇用とセットで導入された年功序列は、技術やノウハウの継承に有効で、社員は一つの企業に長く勤めることで安定した生活を約束され、企業は熟練した労働力を確保できるという、労使双方にとって利点のある仕組みとして機能しました。
特に、一つの製品を完成させるために多くの社員が長期間にわたって協調して作業にあたる自動車産業や電機メーカーなどの「製造業」で、年功序列は大きな役割を果たしました。
組織全体の生産性を高め、日本の経済成長を力強く支えた年功序列は、成果よりも勤続年数が評価されるため、社員は長期的なキャリアプランを描きやすく、一つの会社で長く働くことへの安心感を得ることができます。
これにより、会社への忠誠心や連帯感が醸成され、年功序列の企業は組織としての一体感も高まります。
また、新人教育に時間をかけ、じっくりと専門スキルを身につけさせることができるため、年功序列の企業では、長期的な視点での人材育成が可能です。
一方で、課題もあります。
年功序列の企業では、成果が給与や昇進に直接的に反映されにくいため、高い成果を出している優秀な若手社員の意欲が低下してしまう可能性があります。
また、能力が低くても勤続年数が長いというだけで高いポジションに就いてしまう社員もおり、組織の活力が失われたり、新陳代謝が滞ったりする原因にもなりかねません。
勤続年数が長くなれば、それだけ人件費がかかってしまうという問題も無視できないでしょう。
こうしたさまざまなデメリットが取り沙汰された影響もあり、90年代に入ってからは、成果主義制度やジョブ型雇用に移行する日本企業も増えてきました。
少し古い資料ですが、厚生労働省の「就労条件総合調査」(2004年)によると、個人業績を賃金に反映させている企業は全体の53%に達していました。
つまり、多くの企業が年功序列ではなく、成果主義を取り入れ出したということです。
ライフワークバランスが年功序列の再評価に
時代の移り変わりと共に、成果主義を採用する企業が増えてきたからこそ、年功序列を望む声が増えているという今回の調査結果は、大きな反響を呼びました。
この背景には、不安定な社会情勢や、成果主義がもたらす過度な競争への疲弊があると考えられています。
年功序列には安定した働き方を前提とする側面があるため、精神的な安心感を求める若者にとっては魅力的に映ります。
近年はライフワークバランスを重視する価値観の影響もあり、評価が流動的な成果主義よりも、生活設計のしやすい年功序列が再評価されているという面もあるでしょう。
企業においては、こうした年功序列を望む声に向き合いながら、自社の人事制度を再考する必要が出てきているのかもしれません。
では、年功序列が適している組織とは、どのような組織なのでしょうか。
年功序列が適しているのは、長期的な視点での人材育成が不可欠な組織です。
具体的には、熟練した技術や知識の継承が重要な役割を果たす伝統的な製造業や研究開発部門、あるいは公共性の高い事業を担うインフラ関連企業などがあげられます。
これらの組織では、すぐに結果が出るような仕事は少なく、長年にわたる経験と知識の蓄積が組織の競争力に直結します。
ベテラン社員が持つ暗黙知を若手に伝え、組織全体で時間をかけて成長していくことが求められるため、年功序列の仕組みが有効に機能します。
一方、年功序列が適さないのは、IT業界やWebサービス、コンサルティングファームなど変化の激しい業界や、個々の成果が明確に評価されやすい組織です。
これらの組織は、市場や技術の動向が目まぐるしく変化するため、スピーディーな意思決定と実行が不可欠です。
個々の社員の能力やアイデアが直接的に事業の成功を左右するため、年齢や勤続年数に関係なく、成果を出した社員を正当に評価し、抜擢する成果主義の方が適しています。
また、クリエイティブな仕事や新しい価値の創出が求められる組織では、年功序列が個々の創造性を妨げる危険もあるでしょう。
年功序列制度は、決して古いものではなく、組織の特性や事業内容によっては、今なお有効に機能する可能性が高い制度の一つです。
重要なのは、自社の事業や組織風土を深く分析し、どのような人材が、どのような働き方で活躍できるのかを見極めることです。
そのうえで、自社に最も適した人事評価制度を設計していくことが大切です。
2025.11.06【労働法】売上や融資にも悪影響?『最低賃金法』を守らないリスク
経営改善のために、多くの企業が人件費の削減に取り組んでいます。
しかし、人件費を削減したいからといって、従業員に支払う賃金が国の定める最低賃金を下回ってしまうと、違法経営として厳しく罰せられてしまいます。
最低賃金法に違反した場合、法的な罰則はもちろんですが、それ以上に企業経営全体に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
世間一般から最低賃金法を守らない、いわゆる『ブラック企業』とみなされることで、さまざまな問題が生じるリスクがあるでしょう。
最低賃金を下回った企業が負うことになるリスクについて解説します。
最低賃金の基礎知識と法的ペナルティ
最低賃金とは、国が定めたすべての労働者に最低限支払うべき賃金の額のことで、特定の地域に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に適用される「特定最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金は原則として毎年改定され、2025年度は全国平均で1,121円となりました。
地域別に見てみると、最高額が東京の1,226円、最低額は高知、宮崎、沖縄の1,023円で、初めてすべての都道府県で1,000円を超えました。
そして、この最低賃金を守ることを定めた法律が「最低賃金法」です。
最低賃金法は、企業に対して、労働者の賃金が定められた最低賃金よりも低くならないよう義務づけており、企業が最低賃金を下回る賃金で労働者と合意したとしても、その合意は法律上無効となり、最低賃金額での契約が結ばれたとみなされます。
もし、企業が最低賃金法に違反すると罰則が科せられる場合があります。
最低賃金法では、使用者が地域別最低賃金の定めに違反した場合、50万円以下の罰金に処せられることが定められており、1人の労働者に対して違反があった場合でも適用される可能性があります。
さらに、法的な罰則だけでなく、行政指導や行政処分の対象にもなります。
違反企業は労働基準監督署の立ち入り調査により助言指導や是正勧告などの行政指導が行われ、是正報告書の未提出など改善が見込まれない場合や悪質な場合などは罰則の適用、労働基準関係法令違反として書類送検に加え、厚生労働省や各都道府県労働局のホームページで企業名公表となります。
企業イメージの低下や人材確保への悪影響も
最低賃金法に違反した企業は、労働者に対して本来支払うべきだった最低賃金との差額である「未払い賃金」を支払わなければなりません。
労働者がみずから未払い賃金を請求してきた場合、企業は過去にさかのぼって差額分を支払う義務があります。未払い賃金の請求は、たった1人の労働者からの請求であっても、その影響は決して小さくありません。
未払い期間が長ければ、金額は想像以上に膨らみますし、未払い賃金の請求が行われたことがほかの従業員に知れ渡れば、連鎖的に請求が起こる可能性もあり、その結果、企業の資金繰りを大きく圧迫することになります。
さらに、従業員との関係も悪化し、訴訟に発展するケースも考えられます。
その場合は、本来の未払い賃金に加えて、遅延損害金や弁護士費用なども負担することになる場合もあり、企業の経営を揺るがす事態に発展しかねません。
また、最低賃金法違反は、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、厚生労働省のWebサイトに掲載されることがあるため、もし公表された場合は、企業イメージや売上の低下につながるおそれがあります。
現代はインターネットやSNSを通じて、企業の評判はあっという間に広まります。
もし、自社が最低賃金を守っていないことが知れ渡れば、『ブラック企業』というレッテルを貼られ、消費者からの信頼も失う可能性があるでしょう。
特に、若年層や社会的責任を重視する消費者は、企業の倫理観を厳しく見ています。
たとえ高品質な商品やサービスを提供していたとしても、企業の労働環境が不健全であれば、そのブランド価値は大きく傷つきます。
一度失った信頼を取り戻すことは非常にむずかしく、長期にわたる経営努力が必要となることに留意が必要です。
当然、最低賃金違反をした企業には、新しい人材が集まりにくくなります。
求職者は企業の口コミサイトやSNSで、その企業の実態を綿密に調べており、最低賃金違反の事実が発覚すれば、優秀な人材ほど、そのような企業を避ける傾向にあります。
同時に、信用調査にも悪影響を与え、融資や新規取引にマイナスの影響が出る可能性もあります。
金融機関は融資の可否を判断する際、企業の財務状況だけでなく、信用情報やコンプライアンス遵守の状況も厳しく審査します。
最低賃金法違反は企業のコンプライアンス意識が低いとみなされ、信用調査において大きなマイナス要因となります。
最低賃金法違反が発覚すれば、新たな取引先との新規取引においても、取引を断られるリスクが高まります。
このように、最低賃金法に違反すると法的な罰則だけにとどまらず、企業イメージの低下や人材確保の困難、信用力の低下といった多岐にわたる深刻なリスクが生じます。
企業の健全な経営には、最低賃金法を正確に理解し、法律を遵守するという姿勢が大切です。
2025.11.06【人的資源】ベテランの知恵を活かす!『世代間交流』で組織を活用性
少子高齢化が進む現代の組織では、豊富な経験と知識を持つベテラン層が定年を迎える一方で、若年人口の減少により、若手社員の採用・定着が追いついていません。
これにより、長年にわたって培われてきた技術やノウハウが組織内で十分に引き継がれないリスクもあります。
一方、多様な働き方が広がる現代の組織では、若手社員の定着率をいかに高めるかが、企業の競争力を左右する重要な課題となっています。
この課題を解決するためのヒントが、『世代間交流』に隠されています。
世代を超えた社員間の交流によるメリットや、組織に定着させるためのプロセスなどを解説します。
ベテランと若手のモチベーション向上に有効
組織における世代間交流とは、異なる世代に属する社員同士が業務やプライベートな場面で互いにコミュニケーションを取り、経験や知識、価値観を共有し、相互に学び合う関係性を築くことを指します。
具体的には、ベテラン社員と若手社員がペアを組んで業務に取り組むメンター制度や、世代を超えて交流できる社内イベント、プロジェクトチームの編成などがあげられます。
これまでの日本企業では、新入社員の研修はOJTが主流で、若手社員は配属先の先輩や上司から業務を教わり、一人前の社会人へと成長していくのが一般的でした。
しかし、これからの時代に求められるのは、単に業務知識やスキルを教えるだけではなく、ベテラン社員が長年培ってきた「仕事に対する姿勢」や「問題解決の考え方」、そして「暗黙知」と呼ばれる言語化がむずかしいノウハウを若手社員に継承していくことです。
世代を超えた積極的な交流は、組織全体に多くの好影響を与えます。
若手社員は、ベテラン社員が持つ専門的な知識やスキルを実践で学ぶことができるうえ、マニュアルだけでは伝わらない細やかな技術や、予期せぬトラブルへの対処法など、経験に裏打ちされた知恵を学ぶことができます。
ベテラン社員の仕事に対する情熱やプロ意識を肌で感じることで、若手社員は仕事に対するモチベーションを高めることができるでしょう。
これにより、仕事や組織への愛着が深まり、結果として離職率の低下にもつながります。
一方、ベテラン社員にとっても、自身の持つ経験や知識が若い世代に求められていると感じることは大きな喜びとなり、仕事へのやりがいも向上します。
また、若手社員と交流することで、新しい技術やトレンド、考え方に触れる機会が増え、自身のスキルをアップデートするきっかけにもなるでしょう。
これにより、組織の活力が全体的に向上し、年齢に関係なく誰もが活躍できる風土が醸成されます。
さらに、ベテラン社員と若手社員という異なる世代の視点が交わることで、化学反応が起こり、これまでになかった画期的なアイデアやイノベーションが生まれることがあります。
ベテランの安定感と若手の創造性が融合することで、より柔軟で革新的な体質へと変わっていくことが期待されます。
組織内の世代間交流を成功させる仕組み
世代間交流を成功させるために、会社はただ場を提供するだけでなく、意図的に仕組みを構築することが重要です。
まず、なぜ世代間交流が必要なのか、その目的を組織全体で共有しましょう。
「若手社員のスキルアップのため」「ベテランのノウハウを継承するため」「チームの結束力を高めるため」など、具体的な目標を設定することで、社員が自主的に交流に参加する動機付けとなります。
また、目的を共有したうえで、交流を促す具体的な仕組みを導入します。
たとえば、メンター制度は世代間交流の最も代表的な例です。
若手社員一人ひとりにベテラン社員をメンターとして割り当て、定期的な面談や共同のプロジェクトなどを設定することで、世代を超えた親しい関係性を築くことができます。
さらに、交流が円滑に進むよう、心理的な安全性を確保することも重要です。
ベテラン社員が若手社員の意見を尊重し、若手社員も臆することなく発言できるような、風通しのよい企業文化を育む必要があります。
そして、物理的な環境も大切です。
休憩スペースやフリーアドレス制の導入など、社員が自然に集まり、会話が生まれるような空間作りを工夫することで、世代間の壁を取り払い、交流を促進することができます。
世代を超えた知恵と活力を循環させる世代間交流は、組織の持続的な成長に不可欠な要素です。
若手社員はベテラン社員から経験と知識を学び、ベテラン社員は若手社員から新しい視点と刺激を得る、この相互作用こそが組織に新たな活力を与え、社員一人ひとりの成長を促すでしょう。
2025.10.16【労働法】『固定残業制度』を導入して適正に運用するには
「固定残業制度」は、多くの企業で導入されている賃金制度の一つで、あらかじめ給与のなかに一定の時間外労働に対する手当を含めるというものです。
固定残業制度は、運用を誤ると労働法違反に抵触する可能性がありますが、適切に運用すれば、労使の双方にメリットのある制度です。
特に、企業にとっては業務の効率化や従業員のモチベーション向上につながり、働き方改革を推進するうえでの一つの有効な手段となるでしょう。
労働法に違反せず、正しく固定残業制度を導入する際のポイントについて解説します。
固定残業制度のメリットデメリット
2025年2月に、教員の処遇改善を目的とした法改正が行われ、教員に一律で支給されている「教職調整額」が、現在の月給の4%から段階的に引き上げられ、6年後の2031年には10%にすることが決まりました。
公立学校の教員は、業務が広範囲にわたることから、いわゆる「固定残業制度」に近いかたちが導入されており、教職調整額とは時間外勤務手当の代替として支給されている給与の上乗せ分のことを指します。
固定残業制度は、教員のほかにも、さまざまな職種や企業で採用されている制度です。
給与の一部として、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働などに対する割増賃金を「固定残業代」としてあらかじめ支払うという制度で、従業員は残業をしなくても固定で手当を受け取ることができ、企業側は毎月の給与計算の手間を軽減できるというメリットがあります。
また、時間内に仕事を終えれば終えるほど、従業員の時給単価が高くなるため、業務効率の改善につながることも大きな利点といえるでしょう。
一方で、固定残業制度にはデメリットも存在します。
制度の運用方法を誤ると、従業員の労働時間管理がおろそかになり、結果として長時間労働を助長してしまうリスクがあります。
こうしたリスクは「給与に残業代が含まれているのだから、残業をさせなければいけない」といった企業側の認識不足や、従業員側の「給与に含まれているので、いくら残業しても残業代は支払われない」といった誤解によって、サービス残業が常態化してしまうケースもあります。
固定残業制度では、あらかじめ定められた時間を超えた場合、追加で残業代を支給しなければいけないことを労使の双方が理解しておきましょう。
また、従業員の残業時間が規定に届かなくても、固定で残業代を支払うことになるため、運用の仕方によっては人件費が増加してしまう可能性もあります。
労働法違反になってしまうケースとは
固定残業制度は、その内容があいまいになりがちなため、違法と判断されるケースが少なくありません。
たとえば、給与明細で固定残業代が基本給に含められ、どの部分が固定残業代なのかがわからない状態は違法となります。
固定残業代はどの時間分なのか、いくら支払われているのか、実際の残業時間がどのくらいの時間だったのかを明確にする必要があります。
もちろん、基本給と固定残業代を合算した給与額が、最低賃金を下回っている場合や、固定残業代部分の単価が法定の割増率を下回っている場合なども違法です。
最低賃金に関しては、原則として、固定残業代を除く基本給だけで定められた最低賃金額に達している必要があります。
また、前述した通り、固定残業代として設定した時間を超えて従業員が残業した場合、その超過分については追加で残業代を支払わなければなりません。
この超過分の支払いを怠ると、労働基準法違反となります。
これらを遵守しなければ、制度が無効とみなされ、過去にさかのぼって未払い残業代の支払いを命じられることがあります。
制度の導入を検討する際は、これらの法的要件を十分に理解し、透明性の高い運用を心がけることが重要です。
固定残業制度を導入する際のポイント
企業が固定残業制度を導入するためには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
まず、最も重要なのは、制度の内容を就業規則に明記することです。
具体的には、固定残業代の算定根拠となる時間数、金額、そして超過した分の残業代の計算方法や支払い方法について、誰が見ても明確に理解できるように記載する必要があります。
この際、なぜこの制度を導入するのか、どういった目的で運用していくのか、といった会社の姿勢もあわせて示すことで、従業員からの理解を得やすくなります。
次に、労働契約書や雇用契約書にも固定残業制度の内容を反映させます。
就業規則に加えて、個々の労働契約書にも固定残業代の項目を設け、従業員一人ひとりが制度の内容を理解し、同意してもらうようにします。
新しい制度の導入は、従業員に不安を与える場合があります。
なぜこの制度を導入するのか、従業員にとってどのようなメリットがあるのか、疑問や不安を解消するための対話の場を設けることも有効です。
これまで通り、労働時間の管理を徹底することも忘れてはいけません。
固定残業制度を導入したからといって、労働時間の把握義務がなくなるわけではありません。
むしろ、固定残業時間を超えないよう、これまで以上に厳密な労働時間管理が求められます。
固定残業制度は、適切に運用すれば、企業と従業員の双方にメリットをもたらす有効な賃金制度ですが、その運用には法的要件や注意点があります。
導入を考えているのであれば、労務の専門家などと十分に相談し、自社の実情に合ったかたちで導入を進めていきましょう。
2025.10.16【人的資源】参加強要はNG!? ハラスメントにならない忘年会や新年会の開き方
年末年始に開催される忘年会や新年会は、企業文化を形成するうえで重要なイベントの一つです。
しかし、その一方で、仕事の延長上にない飲み会への強制参加はハラスメントにあたるのではないかという見方も広がっています。
忘年会や新年会は、社員への感謝と慰労を目的に行うものですが、その対象となる社員から不満の声があがるのであれば、実施しないという選択肢もあるのかもしれません。
多くの会社にとって、毎年の恒例行事となっている忘年会や新年会について、考えてみたいと思います。
飲み会への強制参加がハラスメントになる?
会社が主導となって開かれる忘年会や新年会は、一年間の努力を労い、社員が気持ちをリフレッシュして次の仕事に臨めるようにするためのものです。
また、慰労の場であると同時に、社員間の親睦を深めてチームワークを強化するための場でもあります。
普段の業務ではなかなか話す機会がない部署のメンバーや上司、部下と交流することで、人間関係が円滑になり、コミュニケーションが活性化します。
しかし、こうした会社側の狙いが必ずしも成功するわけではありません。
社員によっては、強制的に参加させられる忘年会や新年会を、ハラスメントの一種ととらえる向きもあるようです。
現代の職場において、ハラスメントに対する意識は非常に高まっています。
忘年会や新年会への参加を強制することは、社員の自由な意思を尊重しない行為であり、状況によっては精神的な苦痛を与えるハラスメントとみなされる可能性があります。
では、具体的にどのような場合に、飲み会の参加強制がハラスメントと判断されるのでしょうか。
厚生労働省が定義する「パワーハラスメント(パワハラ)」の類型には「精神的な攻撃」や「人間関係からの切り離し」といった要素が含まれます。
たとえば、忘年会や新年会に「参加しないと今後の人事評価に響く」「チームの一員として認めない」といった発言や示唆があった場合は、明らかなパワハラとなります。
また、直接的な発言がなくても、参加しない社員だけが情報共有から外されたり、露骨に避けられたりするような雰囲気をつくり出すことも、パワハラとみなされるケースがあります。
さらに、一度、社員が断っているにもかかわらず、何度も参加を強要したり、しつこく誘ったりする行為も、精神的な負担を与えるため、パワハラに該当する可能性があります。
特に、上司と部下など明確な上下関係があるうえでの行為は、その立場を利用したハラスメントと判断されやすくなります。
「任意参加」が忘年会などの開催のポイント
会社側は、忘年会や新年会など、飲みの席でのハラスメントにも注意する必要があります。
人によっては、アルコールが入ることで、普段はしないような言動が出てしまうことも少なくありません。
最も典型的なのが飲酒の強要です。
無理にお酒を飲ませようとする行為は「アルコールハラスメント(アルハラ)」であり、パワハラの一種です。
当然、酒の席だからといって、部下や同僚を嘲笑したり、プライベートな話題を暴露したりする行為もパワハラです。
また、性的な言動や身体に触れる行為、プライベートな質問などは「セクシャルハラスメント(セクハラ)」に該当する可能性があります。
これらのハラスメントは、被害者の精神的な苦痛はもちろんのこと、優秀な人材の離職につながる可能性もあります。
ハラスメントのリスクを回避しつつ、社員が楽しめる忘年会や新年会を開催するためには、参加を強制しないことです。
飲み会への強制参加は、ハラスメントになる可能性があるばかりか、賃金の支払義務が発生する可能性もあります。
労働時間と判断された場合、企業は社員に対し、通常の賃金に加えて時間外手当を支払う義務が生じます。
特に、参加が事実上強制されている、業務に関する具体的な指示や役割が与えられている、欠席した場合に不利益が生じるなどの状況では、労働時間とみなされやすくなるので注意が必要です。
忘年会や新年会を開く際には、参加が「任意」であることを強調し、参加しないことによって不利益が生じないことを明確に伝えましょう。
また、参加・不参加の確認は、業務に支障がない範囲で、あくまで個人が選択しやすい方法で行う必要があります。
上司が部下に対し、執拗に参加を促すようなことをしてはいけません。
また、お酒が飲めない人でも参加しやすいように、「ノンアルコールドリンクの充実した店を選ぶ」「食事を中心に楽しめるメニュー構成にする」なども、工夫の一つです。
乾杯の際もアルコールを強要するような雰囲気は避け、ソフトドリンクでの乾杯も容認するなどの配慮をしましょう。
忘年会や新年会は、社員の慰労と親睦を深めるための貴重な機会ですが、状況によってはハラスメントの発生するリスクもあります。
社員一人ひとりの意思を尊重し、誰もが安心して楽しめる場を設けることが、ハラスメントを未然に防ぐことにつながります。
2025.10.02【労働法】『人事異動』に関する労使トラブルを避けるために必要なこと
人事異動は組織の活性化や人材育成に欠かせませんが、労働者にとってはキャリアや生活に大きな影響を与えるため、予期せぬ異動命令に不安を抱く人もいます。
内容次第では「不当な異動命令」として深刻なトラブルを招き、最悪の場合、裁判にまで発展するケースもあります。
特に、労働者の意思に反した不利益な配置転換を強いるような場合は、ケースによって「人事権の濫用」とみなされ、異動命令が無効と判断されてしまいます。
こうした人事異動を巡る労使トラブルを未然に防ぐために、企業が押さえておくべきポイントを解説します。
人事権の濫用だと判断されるケースとは
人事異動は、企業にとって、事業の再編や業務効率化を図る手段の一つです。
しかし、労働者にとっては、長年培ってきた専門性を活かせなくなったり、新たな人間関係の構築を強いられたりするもので、大きな負担を抱えてしまう人もいます。
特に、育児や介護といった家庭の事情を抱えている労働者にとっては、勤務地や勤務時間の変更が生活そのものを揺るがす大きな問題となることもあります。
こうした状況下で、企業側の意図が伝わらず、配慮もないまま異動命令が出されると、労働者は不満や不信感を募らせてしまいます。
これがトラブルの火種となり、最終的には異動命令の有効性を巡る法的な争いに発展することもあります。
企業には、業務上の必要性に基づいて労働者の配置や職務内容を変更する「人事権」が認められています。
しかし、この人事権は無制限に行使できるわけではありません。
労働契約法第3条には、権利の濫用は許されない旨が定められており、人事権の行使もこの原則に従う必要があります。
過去の裁判例では、「業務上の必要性が存在しない異動」や「労働者が受ける不利益が著しく大きい異動」などが人事権の濫用と判断されたことがありました。
たとえば、特定の従業員を退職に追い込む目的で、わざと業務内容とまったく関係のない部署へ異動させるようなケースは、業務上の必要性がある異動とはいえません。
また、育児や介護といった特別な事情を抱えている労働者に対して、その事情を十分に考慮せずに遠方への転勤を命じるようなケースは、労働者の受ける不利益が著しく大きいといえるでしょう。
このように、権利の濫用だと判断されれば、その異動命令は無効となる可能性があります。
ほかにも、労働契約で職種が明確に特定されている場合における使用者による職種変更の命令は、原則として契約に反するため、認められていません。
したがって、職種変更に伴う異動も原則として認められないことになります。
ただし、就業規則などにより職種変更の可能性があらかじめ示されている場合には、一定の範囲で許容されることもあります。
異動命令の根拠を確保するために必要なこと
人事異動を巡るトラブルを未然に防ぐためには、労働契約を締結する際に、労働者の職務内容や勤務地をどこまで限定するのかを明確に定めておくことが重要です。
労働契約書や就業規則に「会社は業務上の都合により、配置転換や転勤を命じることがある」といった包括的な規定を盛り込んでおくことで、異動命令の根拠を確保できます。
ただし、前述した人事権の濫用の原則は常に適用されることを忘れないようにしましょう。
また、異動命令を出す際には、その業務上の必要性と異動の目的を丁寧に説明することが求められます。
労働者が納得しやすいように、なぜこの異動が必要なのか、異動先でどのような役割を期待しているのかを具体的に伝えることで、労働者の不安や不信感を和らげることができます。
一方的な命令ではなく、対話を通じて理解を求める会社側の姿勢が、労使トラブル回避につながります。
さらに、育児や介護、あるいは健康上の問題など、労働者が抱える個別の事情には最大限の配慮が必要です。
まずは労働者本人から丁寧にヒアリングを行い、個々の事情を把握したうえで、異動の時期や内容を調整できないか検討しましょう。
人事異動は、企業経営において欠かせない重要なプロセスですが、その実施方法によっては、深刻な労使トラブルを引き起こすリスクもあります。
会社側の都合だけで一方的に進めるのではなく、労働者の生活やキャリアに与える影響を考慮し、丁寧なコミュニケーションと配慮を心がけることが、労使トラブル回避のカギとなります。
人事異動は業務命令というだけではなく、労働者のキャリアアップや組織全体の活性化につながるポジティブな機会としてとらえ、労使双方にとって納得感のある人事異動を目指しましょう。
2025.10.02【人的資源】『リテンション』における労働環境を整備する重要性
「リテンション」は「保持」や「維持」を意味する言葉で、人事においては、優秀な従業員に長く会社で活躍してもらうための取り組みを意味します。
多くの会社がリテンション施策として、給与や賞与といった金銭的報酬の引上げを検討します。
しかし、それだけでは従業員をつなぎ止めることはできません。
従業員の期待に応えるためには、非金銭的な報酬である「働きやすい労働環境の整備」が不可欠になります。
リテンションを成功させるカギとなる「労働環境整備の重要性」について、解説します。
リテンション施策の金銭的・非金銭的報酬
労働人口の減少が進むと同時に、昔よりも転職のハードルが低い現代において、企業が優秀な人材を確保し続けることは、ますます困難になっています。
一度採用した人材に長く働き続けてもらうことは、企業の成長に欠かせない要素といえます。
「リテンション」によって優秀な従業員が定着すれば、新規採用にかかるコストが削減できますし、従業員の持つ知識や経験が組織内に蓄積され、業務の効率化や品質向上につながります。
さらに、従業員の定着率が高い会社は、企業文化が安定し、従業員間の信頼関係も深まります。
これは新たなイノベーションを生み出す土壌となり、組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。
具体的なリテンション施策は、大きく分けて「金銭的報酬」と「非金銭的報酬」の二つに分けることができます。
金銭的報酬とは、給与や賞与、手当など、直接的に金銭で支払われるものを指します。
公正な評価制度に基づく昇給や、業績に応じたインセンティブなどは、従業員のモチベーションを高めるうえで非常に有効な手段です。
一方で、非金銭的報酬とは、お金には換算できないものの、働くうえで従業員の満足度を高める要素を指します。
たとえば、働きがいのある仕事、良好な人間関係、スキルアップの機会、働きやすい労働環境などが非金銭的報酬に該当します。
多くの企業が金銭的報酬に注力しがちですが、現代の多様な価値観を持つ従業員にとっては、非金銭的報酬も重要な基準となります。
働きやすい労働環境を実現する取り組み
非金銭的報酬のなかでも特に重要なのが、「働きやすい労働環境」です。
労働環境は、従業員の心身の健康と、仕事へのエンゲージメントに直結しています。
長時間労働が慢性化している環境では、従業員の心身の健康を損なうリスクが高まりますし、そうした状況では、本来のパフォーマンスを発揮することがむずかしくなり、結果として離職へとつながります。
一方、働きやすい労働環境が整備されていれば、従業員は仕事とプライベートのバランスを取りやすくなります。
心に余裕が生まれ、仕事への意欲や創造性が高まることで、生産性の向上にもつながりますし、会社に対する信頼感や帰属意識も深まるでしょう。
では、具体的にどのような取り組みが、働きやすい労働環境の整備につながるのでしょうか。
基本になるのは「柔軟な働き方の導入」です。
近年、多くの企業で導入が進んでいるのが「フレックスタイム制」や「勤務間インターバル制度」などです。
制度を導入することで、育児や介護と仕事を両立させたい従業員や、通勤時間の負担を減らしたい従業員が自分に合った働き方を選択できるようになります。
厚生労働省の公表した資料によれば、フレックスタイム制の労働者のほうが通常の勤務時間制度の労働者より、同一企業での就業継続を希望する割合が高く、また、勤務間インターバル制度を採用している企業の正社員のほうが、していない企業の正社員よりも働きやすさを感じていることがわかっています。
柔軟な働き方は、従業員のワークライフバランスを向上させ、離職の大きな要因の一つである家庭と仕事の両立がむずかしいという悩みを解消する手助けとなります。
また、健康経営の推進も重要な施策です。
定期的な健康診断の受診率の向上だけでなく、ストレスチェックの実施や、メンタルヘルスに関する相談窓口の設置など、従業員の健康を経営的な視点からとらえ、戦略的に取り組むことが労働環境の改善につながります。
さらに、オフィス環境も労働環境の要素の一つです。
快適な休憩スペースの整備や、スタンディングデスクの導入など、従業員がリフレッシュできるような工夫をすることで、心身ともに健康的に働ける環境を整えることができます。
リテンションは、単に給与を上げる金銭的報酬だけでは成功しません。
従業員の多様な価値観に応え、長く安心して働ける環境を整えることが何よりも重要です。
働きやすい労働環境を整備するための施策は多岐にわたるため、十分に検討したうえで、自社に合わせた施策に取り組んでいくことが大切です。
2025.09.18【労働法】『解雇規制緩和』の将来的な可能性と現行ルール
2024年の自民党総裁選では「解雇規制の緩和」がテーマの一つとなり、SNS上でも多くの議論を巻き起こしました。
解雇規制とは、企業による従業員の解雇を制限する日本の労働法上の仕組みであり、これを緩和することで、企業は柔軟な人員配置が可能になり、結果として雇用の流動性が高まることが期待されています。一方で、労働者の雇用が不安定になるのではという懸念もあります。
日本では労働者を保護するため、特に解雇に関しては厳しい規制が行われています。
企業の人材戦略に大きく関わる解雇規制の将来的な見通しと、現行ルールの要点について解説します。
解雇規制緩和のメリットとデメリット
「解雇規制の緩和」とは、労働契約における企業の解雇する権利を、現行法よりも広く認めようとする政策的な動きを指します。
現在の日本において、企業が従業員を解雇するためには、客観的かつ合理的な理由が必要であり、社会通念上相当であると認められなければいけません。
労働契約法でも「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。
こうした解雇規制は、労働者の生活の安定と雇用の保障を目的としたものですが、一方で規制が厳しすぎると、企業が新たな人材を採用する際のリスクとなり、雇用の創出を妨げることにもなりかねません。
そこで、解雇規制を緩和することで、企業が経営環境の変化に迅速に対応できるようになり、結果として労働市場の活性化につながるのではないか、という議論が交わされました。
企業としては、人材の流動性が高まり、企業の競争力向上につながる点が解雇規制緩和の大きなメリットになります。
問題のある従業員などに対し、解雇という選択肢を取りやすくなることで、組織の活性化が期待できるようになるでしょう。
採用への心理的・制度的ハードルが下がることで、企業はより積極的に人材を採用できるようになり、新たな事業展開やイノベーションを後押しする可能性もあります。
一方、解雇規制緩和によるデメリットも無視できません。
雇用の不安定化や失業リスクが高まることで、従業員のモチベーションの低下や、組織への不信感の高まりにつながる可能性があります。
結果として従業員の帰属意識が低下し、生産性の減退を招く懸念もあります。
また、優秀な人材も転職しやすくなるため、自社の貴重な人材が流出するリスクが高まります。
人材の入れ替わりが激しくなれば、採用活動にかかるコストや手間が増大することも避けられないでしょう。
解雇規制緩和の議論はまだ始まったばかりですが、こうしたメリットとデメリットのバランスは緩和の是非を語るうえでの重要な視点になります。
現行法で定める解雇ルールと企業の対応方針
現在の労働法制において、解雇は主に「労働基準法」と「労働契約法」によって厳しく規制されています。
労働基準法で特に重要なのは、「解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をしなければならない」という「解雇予告の義務」です。
もし、30日より短い期間で解雇する場合は、その短縮した日数分の平均賃金(解雇予告手当)を従業員に支払う必要があります。
この手当を支払わずに即日解雇を行なった場合、労働基準法違反として行政指導や是正勧告の対象となる可能性があります。
また、同法では、一定の期間中における解雇は、原則として禁止されています。
たとえば、従業員が業務中に負傷したり病気になったりして療養のために休業している期間、およびその後30日間は解雇ができません。
また、女性従業員が産前産後の休業を取得している期間、およびその後30日間も同様に解雇が制限されます。
さらに、労働基準法以外でも、労働組合法では「労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇」を、男女雇用機会均等法では「労働者の性別を理由とする解雇」を禁じています。
そして、労働契約法における解雇規制は、より広範な解雇の有効性を判断する基準となります。
同法に示されている通り、解雇には客観的かつ合理的な理由が必要になります。
たとえば、従業員の勤務態度に問題がある場合でも、企業はいきなり解雇するのではなく、注意指導を行い、改善のための機会を与えるなど、解雇を回避するための努力を尽くすことが求められます。
それでも改善が見られない場合に限り、解雇の有効性が認められる余地が生まれます。
今後、解雇規制がどのように変化していくかは、経済情勢、社会情勢、そして政治的な動向によって左右します。
しかし、どのような変化があったとしても、企業としては、常に労働関係法令を遵守し、従業員との良好な信頼関係を築くことが、安定した経営の基盤となります。
将来的な制度変更を注視しつつも、まずは現行ルールの正確な理解と適切な労務管理を行なっていきましょう。
2025.09.18【人的資源】部下のやる気を削ぐ細かい指導『マイクロマネジメント』とは
多くの上司やリーダーは、部下や新人の成長を願い、細部にわたるまで熱心に指導します。
しかし、その熱心さが、もしかしたら「マイクロマネジメント」になってしまうかもしれません。
マイクロマネジメントとは、上司やリーダーが部下の業務に対して過度に干渉し、細かな指示や監視を行うことを指します。
一見、新人の育成に役立つように思えますが、実はこの行為が、部下のやる気を大きく削ぎ、組織全体の生産性を低下させる原因となる可能性があります。
組織に悪影響を与えるかもしれない、マイクロマネジメントについて解説します。
マイクロマネジメントが起きてしまう背景
「マイクロマネジメント」とは、上司が部下の仕事の進め方など、細部にわたるまで口を出し、過剰に管理・干渉する状態を指します。
たとえば、部下が作成する資料のフォントサイズから、メールの文面の一言一句まで指示を出したり、進捗状況を分単位で報告させたりするといった行為がマイクロマネジメントに該当します。
部下に任せたはずの業務を、結局は上司自身が手直ししてしまう、といったケースもマイクロマネジメントの一種です。
ほかにも、タスクの進捗を1日何度も確認したり、決裁不要な業務にも許可を求めさせたりすることも、マイクロマネジメントといえます。
このようなマイクロマネジメントが起きてしまう背景には、上司の「不安」が要因の一つとしてあります。
マイクロマネジメントをしてしまう上司は、自分の思い描く完璧な結果を得るために、部下のやり方が少しでも異なると不安になり、細かく介入してしまいます。
上司には部下に対して管理監督責任があり、部下のミスが自身への評価になってしまうという現状も不安を増幅させます。
逆に、自分の指導に過剰な自信を持っている上司も、マイクロマネジメントを起こしやすいタイプです。
実績のある上司は、過去の成功体験から自分のやり方が絶対的に正しいと思い込み、部下にそのやり方を強要してしまう傾向にあります。
ほかにも、上司自身が多忙であるために、部下とのコミュニケーションの時間が十分に取れず、結果として指示が一方的になり、細かくなってしまうこともあります。
組織全体の業務の進捗が不透明である場合も、部下の仕事を細かくチェックせざるを得ない状況に陥ることがあります。
これらの要因が複合的に絡み合い、結果として部下の自律性を奪うマイクロマネジメントへとつながってしまいます。
上司がよかれと思って行なっている指導が、実は部下のやる気を削いでいる可能性があるということをまずは認識することが重要です。
マイクロマネジメントが組織の生産性を低下
マイクロマネジメントは、部下のモチベーションを低下させるだけでなく、その人の成長機会を奪うことにもなります。
自分で考え、試行錯誤する機会がなければ、部下は成長できません。
失敗から学ぶことも、成功体験を積み重ねることもできず、いつまで経っても上司の指示がなければ動けない「指示待ち人間」になってしまいます。
これは将来のリーダー候補を育成するうえでも、大きな損失といえるでしょう。
また、業務効率の低下と生産性の悪化も避けられません。
上司が部下の業務に過度に介入することで、確認や承認のプロセスが増え、仕事のスピードが落ちてしまいます。
上司自身も部下の仕事の細部にまで気を取られるため、本来集中すべきマネジメント業務や戦略立案に時間を割くことができなくなり、結果として組織全体の生産性が低下します。
このような組織に悪影響を与えるマイクロマネジメントを企業として防ぐためには、上司自身のマネジメントスキルを向上させる必要があります。
前述した通り、マイクロマネジメントをしてしまう上司は、不安を抱えていることが少なくありません。
コーチングスキルを学ばせる、リーダーシップ研修に参加させるなど、上司のマネジメント能力を高め、不安を払拭させることが、結果的に部下の成長を促し、よりよいチームを築くことにつながります。
また、失敗を許容する企業文化の醸成も非常に重要です。
挑戦には失敗がつきものですが、その失敗を過度にとがめるのではなく、「次への学び」としてとらえる文化が組織に根付けば、部下は恐れることなく新しいアイデアを試し、困難な課題にも積極的に取り組めるようになるでしょう。
そして、上司自身も、部下の失敗を自分の責任として受け止められるようになるはずです。
部下を細かく管理することは、一見すると責任感の表れのように見えますが、実際には部下の成長を阻害し、モチベーションを低下させ、ひいては組織全体の活力を奪うことにつながりかねません。
部下一人ひとりが主体性を持って業務に取り組むことができる組織は、変化の激しい現代において、持続的に成長していける強い組織といえます。
まずは組織内でマイクロマネジメントが起きていないか調査し、可視化してみることをおすすめします。
2025.09.04【労働法】年次有給休暇『計画的付与制度』の活用法と導入時の留意点
2023年の年次有給休暇(以下、有給休暇)の取得率は65.3%と過去最高を記録しましたが、政府が目標として掲げる70%には到達していません。
そのようななか、有給休暇の取得を促進し、従業員のワークライフバランスを向上させる制度として注目を集めているのが、有給休暇の「計画的付与制度」です。
この制度は、労使協定を締結することで、企業が有給休暇の取得日をあらかじめ設定できるというものです。
従業員はためらうことなく有給休暇を取得でき、企業は計画的な事業運営が可能になるなど、さまざまなメリットのある計画的付与制度について解説します。
制度利用で有給休暇の取得率向上に期待
有給休暇の「計画的付与制度」とは、労働基準法第39条に基づいて設けられた制度で、使用者は有給休暇のうち5日を超える部分について、労使協定に基づいて、計画的に休暇日を定めることができます。
たとえば、年10日の有給休暇が付与される従業員の場合、自由取得分の5日を除いた残りの5日が計画的付与の対象となり、年間20日付与される従業員であれば15日が対象となります。
2019年4月から施行された「有給休暇の取得義務化」により、使用者は年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、毎年5日以上の有給休暇を取得させる義務を負うことになりました。
しかし、企業によっては、「忙しくて休めない」「同僚に迷惑をかけたくない」などの理由から、従業員がなかなか有給休暇を取得しきれない現状があります。
有給休暇の取得率向上は、多くの企業にとって長年の課題でした。
計画的付与制度を導入するメリットの一つに、この有給休暇の取得率向上があります。
従業員は会社が休暇日を定めることで、気兼ねなく休暇を取得できるようになります。
十分な休暇が取れれば、心身のリフレッシュを図ることができ、疲労回復やストレス軽減にもつながるでしょう。
また、有給休暇の取得が進むことで、従業員のワークライフバランスが向上し、企業に対するエンゲージメントやロイヤルティが高まることも期待できます。
一方、企業にとっては、従業員の休暇日が事前に明確になるため、業務の年間計画や月間計画を立てやすくなります。
これにより、人員配置や生産スケジュールを最適化し、業務の停滞や遅延を防ぐことができます。特に、後述する一斉付与方式であれば、業務を完全に停止させる期間を設けることで、設備の保守点検や社員研修などを効率的に実施することも可能です。
計画的な休暇取得は、業務の属人化を防ぎ、組織全体の生産性向上につながります。
つまり、有給休暇の計画的付与制度は、労働者の権利である有給休暇の取得を促し、企業側にとっても計画的な業務運営を可能にする、労使双方にメリットのある制度といえます。
業種や業務内容によって最適な方式を選択
計画的付与制度には、主に3つの付与方式があります。
事業場全体の休業による「一斉付与方式」は、企業全体あるいは部署全体で一斉に有給休暇を取得させる方式です。
代表的なものとしては、夏季休暇や年末年始休暇、ゴールデンウィークの飛び石連休を計画的付与による連続した休暇にするケースです。
製造業などで生産ラインを停止させる場合や、オフィス業務が完全に停止できる企業などでは非常に効果的な方法です。
班・グループ別の「交替制付与方式」は、サービス業や流通業など、事業を完全に停止することがむずかしい企業に適した方式です。
従業員を複数の班やグループに分け、それぞれのグループが交替で計画的に有給休暇を取得するというものです。
たとえば、Aグループが「10月1日から7日」まで、Bグループが「10月11日から17日」までといったように、時期をずらして有給休暇を付与します。
これにより、従業員の休暇取得を促進しつつも、必要な人員を確保し、事業運営を継続することが可能になります。
年次有給休暇付与計画表による「個人別付与方式」は、従業員一人ひとりの事情や希望を考慮し、個別に有給休暇の取得計画を立てる方法です。
たとえば、従業員の誕生日や結婚記念日、家族の行事に合わせて有給休暇を付与したり、閑散期に集中的に取得させたりするケースがあげられます。
企業側は、従業員からの希望を募り、業務に支障が出ない範囲で調整しながら「年次有給休暇付与計画表」を作成し、この計画表に基づいて、個人の休暇日を設定することになります。
どの方式も、企業の業種や業務内容、従業員の働き方などによって向き不向きがあるため、自社に最適な方式を選択することが重要です。
また、計画的付与制度の重要なポイントは、有給休暇の付与日数のうち、最低5日間は従業員が自由に取得できる日として残しておかなければならないことです。
計画的付与の対象となるのは、あくまで5日を超える部分のみです。
この5日は、病気や慶弔など、従業員個人の急な事情に対応するために確保されるべきものであり、労使協定で指定することはできません。
いずれにせよ、計画的付与制度は従業員にとって有給休暇の取得日を会社によって決められるという側面があるため、導入に際しては従業員からの反発や不満が生じる可能性もゼロではありません。
制度導入を検討するのであれば、その目的が、従業員の有給休暇の取得促進であることを丁寧に説明し、従業員の理解と協力を得るようにしましょう。
2025.09.04【人的資源】男性従業員への『パタハラ』に注意!『マタハラ』との違いとは?
子育てのための育児休業や時短勤務などの制度を利用しようとした男性従業員に対して、不利益な扱いをしたり、嫌がらせをしたりすることを「パタニティハラスメント(パタハラ)」と呼びます。
パタハラは、セクハラやパワハラなどと同じハラスメントの一種で、もし組織内でパタハラが起きていれば、会社として早急に対策を講じなければいけません。
そのためには、まずパタハラに対する正しい理解が不可欠です。
パタハラの定義から、その具体例、そして混同されがちな「マタハラ」との違いなどを解説します。
育児関連制度の利用が理由のハラスメント
「パタハラ」とは、育児休業や子の看護休暇、時短勤務といった育児関連制度の利用を希望した男性従業員に対して、職場内で不当な扱いや嫌がらせを行うことを指します。
パタハラが起きる要因としては、「男性は仕事・女性は家庭」といった古くから残る固定観念や、男性従業員が育児休業を取る権利への理解不足などがあり、その多くは上司や同僚からの心ない言動として現れます。
たとえば、育児休業の取得について上司に相談したところ、「男が育休なんて取るな」「休むなら辞めろ」といった暴言を浴びせられたケースなどは、典型的なパタハラといえます。
また、育児休業取得後に不当な異動や降格、減給といった人事上の不利益を与えることもパタハラに該当します。
特に、長時間労働が常態化している職場や、育児休業取得者が少ない職場では、「男性が育児のために休む」という発想自体が受け入れられにくい傾向があります。
こうしたパタハラと並んでよく耳にするのが、「マタニティハラスメント(マタハラ)」です。
マタハラは、妊娠・出産を理由に女性従業員が不当な扱いを受けることを指します。
パタハラが男性従業員を対象とし、「育児休業取得への理解不足」や「男性の育児参加への偏見」が主な要因であるのに対し、マタハラは女性従業員が対象となり、「妊娠・出産による体調変化への配慮不足」や「産休・育休の取得が当然とみなされること」への反発などが要因となります。
パタハラもマタハラも、対象となる従業員や発生する背景に違いはあるものの、育児関連制度の利用を理由としたハラスメントであるという点では共通しています。
どちらも、企業が早急に対策しなければいけない課題となっています。
「育児休業等に関するハラスメント」を防ぐには
育児・介護休業法においては、パタハラやマタハラなどの「育児休業等に関するハラスメント」の防止措置が事業主に義務づけられています。
企業は、ハラスメントを許さないという方針を明確にし、就業規則や社内報などで従業員に広く周知しなければいけません。
同時に、ハラスメントに関する相談窓口を設け、従業員が安心して相談できる環境を整える必要があります。
その際には、相談者のプライバシー保護を徹底し、相談したことで不利益な扱いを受けないことを保証することが重要です。
さらに、単に規則を定めるだけでなく、組織風土そのものを変革していくことも、パタハラを防止するためには重要です。
大切なのは、組織の経営層や管理職が育児休業制度に関する正しい知識を持ち、男性従業員の育児参加に対して理解を示すことです。
会社全体で育児休業の重要性や男性の育児参加を積極的に支持する姿勢を示すことは、従業員の意識を変えるうえで非常に大きな効果があります。
たとえば、経営層がみずから育児休業を取得したり、男性従業員が育児制度を利用することを推奨したりする具体的なメッセージを発信することで、組織をポジティブな方向へ導くことができるでしょう。
また、ハラスメント防止研修だけでなく、「アンコンシャス・バイアス」に関する研修の実施も検討するとよいでしょう。
アンコンシャス・バイアスとは、自分自身も気づいていない偏見や思い込みのことで、パタハラやマタハラの要因になることも少なくありません。
このような研修を実施することで、「男性が育休を取るなんて」といった社内の無意識の思い込みを是正する効果が期待できます。
育児休業制度についても、使いにくい雰囲気があれば制度が形骸化してしまうおそれがあります。
育児休業を取得する従業員の業務をほかの従業員がスムーズにカバーできる体制を整えるなど、業務フローを見直すと同時に、育児休業期間中の代替要員の確保や、業務の見える化なども進めていきましょう。
パタハラに対する意識を高め、適切な対策を講じることは、すべての企業にとって喫緊の課題の一つです。
全従業員が「育児制度の利用が当たり前」という認識を持てるような取り組みを進めていきましょう。
2025.08.21【労働法】『ストレスチェック』が全企業に義務化へ!企業の対応は?
「ストレスチェック」とは、医師や保健師らが企業の労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査です。
労働安全衛生法では、従業員が常時50人以上の事業所に対してストレスチェックの実施を義務づけています。そして、2025年の同法改正により、従業員50人未満の事業所も段階的にストレスチェックが義務化される予定です。
従業員の心の健康は企業の持続的な成長に欠かせない要素です。
義務化に向けて、対象となる企業が今から行うべき準備について、解説します。
ストレスチェック義務化の対象拡大の背景
近年、働く人々のストレスは多様化し、メンタルヘルス不調を訴える労働者の数も増加傾向にあります。
厚生労働省の労働安全衛生調査によれば、メンタルヘルス不調により休業または退職した労働者がいる事業所の割合は、2020年は9.2%、2021年は10.1%、2022年には13.3%に達しています。
この傾向は大企業に限らず、中小企業においても同様です。
中小企業においては、人材が限られていることや、専門的な相談機関へのアクセス方法が少ないことなどから、一度メンタルヘルス不調者が発生すると、その影響がより深刻になるケースも少なくありませんでした。
そこで、労働安全衛生法の改正によって、現在は努力義務となっている従業員50人未満の事業所についても、ストレスチェックの実施が今後義務化される見通しです。
2025年5月8日に改正労働安全衛生法が可決・成立され、3年以内(2028年まで)に施行される予定です。
この義務化によって、小規模な事業所においても、従業員の心の健康を守るための体制づくりが進められることになります。
これまで大企業では、産業医の選任義務やストレスチェックの義務化など、法に基づいた健康管理体制が整備されてきました。
しかし、従業員50人未満の小規模な事業所では、これらの法的な義務がなかったため、健康管理体制に差が生じていました。
ストレスチェックの義務化は、企業間における健康確保の格差をなくし、すべての労働者が一定水準のメンタルヘルスケアを受けられるようにするための重要な一歩となります。
ストレスチェックの中身と実施する目的
新たに対象となる事業所は、どのような準備を行えばよいのでしょうか。
大切なのは、ストレスチェックの具体的な中身を把握することです。
ストレスチェックとは、医師や保健師などの専門家によって実施される心理的な負担の程度を把握するための検査です。
検査は主に質問票形式で行われ、仕事内容、人間関係、職場環境などのストレス要因、ストレスによる心身の反応、そして周囲からのサポート状況などについて、従業員が回答します。
回答内容は、個人情報保護の観点から、原則として事業者へは本人の同意なしには提供されません。
この年1回のストレスチェックを行うことで、従業員は自身のストレスの状態を把握し、セルフケアに役立てたり、高ストレスと判定された場合には医師による面談指導を受けたりすることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことができます。
対象の事業所が義務化に向けて準備すること
従業員50人未満の事業所にとって、ストレスチェックは新たな取り組みとなります。
まずは、ストレスチェックを実施するにあたり、具体的な実施時期や方法、高ストレス者への対応フローなどを検討し、計画を立てる必要があります。
特に実施者の選定は重要です。
ストレスチェックを行えるのは、医師か保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、公認心理師、精神保健福祉士、歯科医師などに限られています。
自社に該当資格を持つ従業員がいない場合は、外部機関への委託を検討しましょう。
このストレスチェックは、年1回以上の実施が義務づけられていますが、実施時期は自由に設定できます。
従業員の業務負荷が少ない時期や、定期健康診断と同時期に実施するなど、効率的なタイミングを検討しましょう。
また、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員に対しては、医師による面接指導の機会提供や、必要に応じた職場環境の改善策の検討など、具体的な対応フローをあらかじめ定めておくことが重要です。
同時に、制度の導入にあたり、就業規則や安全衛生規程などの社内規定にストレスチェックに関する事項を明記しておきましょう。
こうした規定は制度内容とあわせて、従業員に丁寧に説明し、理解を促すことが大切です。
ストレスチェックの実施は、労働安全衛生法で実施が義務づけられていますが、未実施そのものに罰則はありません。
しかし、実施しなかった場合、安全配慮義務違反と判断される可能性があります。
さらに、ストレスチェックの実施後は、所轄の労働基準監督署へ報告する必要があり、これを怠ったり虚偽の報告をしたりすると、労働安全衛生法違反となり、最大50万円の罰金が科される場合があります。
新たな制度の導入には手間やコストがかかるかもしれませんが、しっかりと準備して実施すれば、ペナルティを受けることもありません。
従業員の心の健康は、企業の生産性の向上や離職率の低下にも影響します。
対象となる事業所は、義務化に向けて今から具体的な準備を進め、必要に応じて外部の専門機関のサポートも活用しながら、従業員が安心して長く働ける職場環境づくりに取り組んでいきましょう。
2025.08.21【人的資源】会社に仕返し!?『リベンジ退職』による被害を防ぐには?
近年、会社への『仕返し』を目的に、意図的なトラブルを起こして退職する従業員が増えてきました。
組織に大きな損害を与える「リベンジ退職」は、企業側にとっても看過できない問題となっています。なぜ、従業員は会社に恨みを抱き、このような行動に出てしまうのでしょうか。
企業がリベンジ退職を防ぐには、その内容や背景を理解しておかないといけません。
リスク管理という観点からも重要な、リベンジ退職の対処法と予防法を解説します。
企業側が受けるリベンジ退職による被害
リベンジ退職とは、従業員が退職する際に、会社に対する不満や恨みから、意図的に業務に支障をきたしたり、企業に損害を与えたりする行為を指します。
具体的には、顧客情報の流出や機密データの持ち出し、SNS上での誹謗中傷、業務の引き継ぎの拒否、悪意のある情報拡散などがあげられます。こうした行為は、単なる迷惑行為にとどまらず、企業の評判を著しく傷つけ、経済的な損失をもたらす可能性があります。
顧客情報や機密データが競合他社に渡れば、企業の競争力が低下して売上に影響が出かねませんし、SNSで悪評が広がれば、企業はブランドイメージを回復するために多大な時間と労力を要することになります。
こうしたリベンジ退職が起きる背景には、従業員が会社に対して抱く「不満」や「不公平感」が大きく関わっています。
長時間労働、ハラスメント、不当な評価、給与への不満、人間関係の悪化など、日々の業務のなかで従業員が積み重ねてきた負の感情が、退職という節目で爆発してしまいます。
また、自由に意見を言えず、不満や問題を上司や会社に相談できない環境では、従業員が不満を内に溜め込んでしまいます。
結果として、その不満が限界に達したときに、リベンジ退職という形で表れてしまうというわけです。
さらに、現代社会における転職市場の活性化も無関係ではありません。
終身雇用という概念が薄れ、転職が当たり前になったことで、従業員は以前よりも気軽に会社を離れることができるようになりました。
そのため、不満を抱えながらも我慢して働き続ける必要がなくなり、退職を機に会社への不満をぶつける行動に出るケースが増えているといわれています。
もちろん、インターネットやSNSの普及も、リベンジ退職を助長する大きな要因となっています。
匿名で情報を発信できる環境が整ったことで、従業員は会社に対する中傷的な投稿や社内情報の漏洩を簡単に拡散できるようになりました。
リベンジ退職の対処法と予防法
もし、リベンジ退職が起きてしまった場合、企業は迅速かつ冷静に対応しなければいけません。
最も重要なのは、被害の拡大を最小限に食い止めることです。
情報漏洩が疑われる場合は、直ちにシステムへのアクセス制限を行い、漏洩経路の特定とデータの保全を行いましょう。
SNSでの誹謗中傷であれば、対象となる投稿の削除依頼を行うと共に、今後の対応について法的な措置も視野に入れる必要があります。
情報漏洩や名誉毀損など、企業に明確な損害が発生している場合は、民事訴訟や刑事告訴といった法的手段を通じて、損害賠償請求や刑事責任の追及を検討することになります。
その際には、専門家である弁護士などと連携し、適切な手続きを踏むことが必須です。
このようにリベンジ退職が起きた際の対処法を考えておくことも大切ですが、一番重要なのはリベンジ退職が起きないようにすることです。
まず、社内のコミュニケーションを活性化し、従業員が安心して意見を言える環境を構築しましょう。
定期的な面談、アンケートの実施、気軽に話せる休憩スペースの設置など、従業員が抱える不満や不安を早期に察知し、解決できる仕組みを整えます。
特に、部下が上司に対して、「この人にだったら相談できる」と思えるような信頼関係がしっかり構築できていると、リベンジ退職が起きる可能性は低くなります。
人事評価制度や報酬制度の透明性を高めることも重要です。
従業員が「なぜ自分はこのような評価なのか」「なぜあの人は昇進したのか」といった疑問を抱かないよう、評価基準を明確にし、フィードバックを丁寧に行うことで、不公平感を解消することができます。
納得感のある評価は、従業員のモチベーション向上にもつながります。
また、ハラスメント対策も徹底します。
セクハラ、パワハラ、モラハラなど、あらゆるハラスメントを許さない企業文化を醸成し、相談窓口の設置や研修の実施を通じて、従業員が安心して働ける環境を構築しましょう。
各種ハラスメントは従業員の心に深い傷を残し、リベンジ退職の大きな要因となり得ます。
リベンジ退職は、現代社会において企業が直面する新たなリスクであり、その被害は計り知れません。
そして、リベンジ退職が生じる根底には、従業員のエンゲージメントの低下があります。
従業員が安心して意見を言える環境を整え、公正な評価と適切な報酬を提供し、ハラスメントのない健全な職場環境を築くことが、リベンジ退職を未然に防ぐことにつながります。
2025.08.7【労働法】『熱中症対策』の義務化がスタート!企業が取るべき対応とは?
近年の夏季は猛暑が続くことが多く、熱中症患者も増加傾向にあり、職場における熱中症対策が大きな課題の一つとなっています。
厚生労働省によって労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日からは、すべての事業者に対して、職場における熱中症対策が罰則つきで義務化されました。これまでの熱中症対策は、あくまで事業者の努力義務とされていましたが、今回の改正によって、より具体的な対策を講じることが求められます。
従業員の健康と安全を守るためにも、義務となった熱中症対策の内容を把握しておきましょう。
熱中症のリスクを判断するための「WBGT」とは
猛暑により職場における熱中症発生のリスクが高まるなか、厚生労働省の発表によれば、熱中症による死亡災害が2年連続で30人を超えたことがわかりました。
死亡者の約7割は屋外作業に従事していましたが、熱中症は屋内においても発生する危険性があります。
特に工場や厨房、倉庫など、熱がこもりやすい場所での作業や、空調設備が不十分な環境では、室温や湿度の上昇により、誰もが熱中症になるリスクがあります。
こうした熱中症による死亡災害の多くが、初期症状の放置および対応の遅れが原因でした。
そこで、職場における熱中症の重篤化を防止するために、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から、すべての事業者に対して、熱中症対策が義務化されました。
対策が必要となるのは、WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の作業場で、連続して1時間以上、または1日当たり4時間を超える作業が見込まれる場合です。
WBGTとは、熱中症の危険度を評価するために用いられる国際的な指標で、単に気温だけでなく、湿度、輻射熱(地面や建物からの熱)も含めた3つの要素を取り入れて算出されます。
これによって、より人体が感じる暑さに近い感覚を数値で表すことができます。
たとえば、気温が同じでも湿度が高いと熱中症のリスクは高まりますし、日差しが強い場所では輻射熱の影響も大きくなります。
これら複数の要素を総合的に判断できるWBGTにより、より正確に熱中症の危険レベルを把握することが可能になります。
重篤化を防ぐために義務づけられた措置
労働安全衛生規則の改正により、事業者に義務づけられるのは「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の3つです。
この3つを軸にしながら、熱中症のおそれがある従業員を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することで、熱中症の重篤化を防ぐことができます。
具体的には、熱中症対策の責任者を明確にし、緊急時の連絡体制や医療機関との連携体制を確立することなどが求められます。
誰が、いつ、どこで、どのような役割を担うのかを明確にすることで、万が一の事態にも迅速かつ的確に対処できるようになります。
熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、それを報告するための連絡先や担当者を事業場ごとに定めておきましょう。
また、事前に手順を作成しておくことも重要です。
作業からの離脱や身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置を事業場ごとにマニュアル化しておくことが、重篤化を防ぐことになります。
さらに、WBGT値に応じた作業の中断基準、休憩の取り方、水分・塩分補給のルール、体調不良者の発見から救急車要請までのフローなどもあらかじめ決めておきましょう。
マニュアルがあれば、誰もが同じ基準で行動でき、対応の遅れや判断ミスを防ぐことができます。
こうした整備された体制や作成された手順を、すべての従業員に徹底して周知します。
全従業員に安全衛生教育の一環として、熱中症に関する知識と対策の重要性を理解してもらうことが、熱中症予防になります。
もし熱中症のおそれのある従業員がいたら
実際に適切な行動が取れるよう、シミュレーションしておくことも大切です。
まず、熱中症のおそれのある従業員を発見したら、直ちに作業を中断させ、涼しい場所へ移動させましょう。
風通しのよい日陰や、エアコンが効いた室内などに移し、衣服を緩め、体を冷やします。
特に首の周り、脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている部分を氷や保冷剤などで冷やすとよいでしょう。
次に、意識の有無を確認します。
呼びかけに反応があるか、意識がはっきりしているかを確認し、返事がおかしい、反応が鈍いなど、普段と様子が異なる場合は熱中症のおそれがあるものとして対応し、迅速に119番へ電話し、救急隊を要請します。
意識がはっきりしており、本人が自分で水分を摂取できる場合は、冷たい水やスポーツドリンク、経口補水液などを少量ずつ繰り返し飲ませます。
救急隊が到着するまで、または医療機関へ搬送されるまでの間は、決して一人にせず、継続して体温を下げる努力を続けます。
体調が回復したように見えても、その後に急変するケースがあるため、経過観察は慎重に行う必要があります。
もし、医療機関への搬送に至らない場合でも、回復後の体調急変に備え、事前に定めた連絡体制に基づき、家族などへの連絡や症状が悪化した場合の対応について確認しておきましょう。
判断に迷うような状況では、安易な自己判断を避け、「#7119(救急安心センター事業)」などに連絡して、専門家の指示を仰ぎましょう。
今回の労働安全衛生規則の改正による熱中症対策の義務化は、従業員の健康と安全を守るうえで極めて大きな意味を持ちます。
夏季はもちろん、梅雨の時期や残暑が厳しい時期など、年間を通して継続的に意識し、従業員の体調管理に気を配ることが重要になります。
2025.08.7【人的資源】政府も後押し!『ジョブ型人事指針』の中身とジョブ型雇用の注意点
2024年8月28日に、内閣官房は「ジョブ型人事指針」を公表しました。
この指針では、ジョブ型人事制度を導入している先進的な20社の具体的な事例を紹介しており、これから導入を検討する企業にとって、非常に実践的な手引きとなるものです。指針の公表は、ジョブ型人事制度への関心が高まっているなかで、その流れをさらに加速させるものとみられています。
一方で、ジョブ型人事に抵抗感を持つ企業も少なくありません。
今回は、ジョブ型人事指針が公表された理由や、ジョブ型人事制度のメリットとデメリットなどを解説します。
「ジョブ型人事指針」が公表された背景
内閣官房が2024年8月28日に公表した「ジョブ型人事指針」は、新しい資本主義実現会議「三位一体労働市場改革分科会」が中心となって策定したものです。
この指針の最大の特徴は、抽象的な概念の説明に留まらず、実際にジョブ型人事制度を導入し、成果を上げている20社の具体的な事例が豊富に盛り込まれている点にあります。
事例は、大企業から中小企業まで、さまざまな業種・規模の企業を網羅しており、各社がどのような課題を抱え、ジョブ型人事制度をどのように設計し、運用しているかが詳細に紹介されています。
具体的には、職務記述書の作成方法、評価制度の見直し、報酬体系の設計、人材育成の考え方など、ジョブ型人事制度を導入するうえで直面するさまざまな課題に対して、具体的な解決策や成功事例が提示されています。
たとえば、ある企業では、各職務に求められるスキルや経験を明確に定義した職務記述書を作成し、それを採用や配置、評価の基準として活用している事例が紹介されています。
また別の企業では、職務等級制度を導入し、職務の難易度や重要度に応じて報酬を決定することで、より公平で透明性の高い評価制度を構築しています。
この指針は、ジョブ型人事制度への移行を考えている企業が、個別の事情に合わせて制度を設計できるよう、多様な選択肢とヒントを提供することを目指しています。
いわば、ジョブ型人事制度を導入するための『羅針盤』のような役割を果たすものといえるでしょう。
では、なぜ政府はこのジョブ型人事指針を公表したのでしょうか。
その背景には、日本企業が抱える構造的な課題があります。
長らく続いてきた年功序列や終身雇用といった制度は、高度経済成長期には安定した雇用を生み出し、企業の成長に貢献してきました。
しかし、グローバル化の進展や国際競争の激化、技術革新などによって環境が大きく変わったことにより、企業はより迅速に市場の変化に対応し、イノベーションを生み出すことが求められるようになりました。
このような状況下で、従来の雇用制度は、従業員の専門性を高めにくい、成果へのインセンティブが働きにくいといった課題を抱えています。
特に、デジタル化の波が押し寄せる現代において、従来のメンバーシップ型では、特定の専門スキルを持った人材を適材適所で配置し、最大限に能力を発揮させるのがむずかしいという実情がありました。
政府は、この指針を通じて、企業が個々の職務に求められる専門性やスキルを明確にし、それに見合った人材を配置・育成するジョブ型人事への移行を促すことで、企業全体の生産性向上と競争力強化を目指しています。
ジョブ型人事のメリットとデメリット
ジョブ型人事制度を導入する際は、メリットとデメリットを把握しておくことが重要です。
メリットとしては、各職務の役割と責任が明確になるため、従業員は自分の職務に集中しやすくなる点です。
これにより、無駄な業務が減り、効率的に仕事を進めることができるため、結果として組織全体の生産性向上につながります。
また、職務内容が明確になることで、企業は必要なスキルや経験を持つ人材をピンポイントで採用し、最適な職務に配置することが可能になります。
従業員自身も専門性を高めるべき方向性が明確になるため、計画的にスキルアップを図り、より高度な専門職として成長していくことができます。
一方、デメリットとしては、ゼネラリストの育成がむずかしくなる可能性があげられます。
職務が明確化されることで、従業員が自身の専門外の業務を経験する機会が減り、幅広い知識や経験を持つゼネラリストが育ちにくくなるかもしれません。
これは、将来の幹部候補の育成において課題となる場合があります。
また、部署間の連携がしづらくなる可能性があります。
職務範囲が明確になることで、自分の担当範囲以外の業務に積極的に関わろうとしなくなり、部署間の情報共有ができない状態である「サイロ化」が生じるリスクがあります。
組織がサイロ化してしまうと部署間の連携が希薄になり、組織全体のパフォーマンスが低下するかもしれません。
ほかにも、制度設計と運用の複雑さや、従業員の意識改革が困難になるなどの課題も考えられます。
このようなメリットとデメリットを十分に理解したうえで、検討することが大切です。
もし、導入する場合は、指針の事例を参考にしながら、自社の状況に合わせた制度の設計を進めていきましょう。
2025.07.17【労働法】改正雇用保険法が施行!『教育訓練給付金』の創設にどう対応する?
2024年5月10日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(改正雇用保険法)」は、多様な働き方を支えるための「セーフティネットの構築」および「人への投資の強化」を目的としており、改正内容は雇用保険の対象拡大や教育訓練支援など、多岐にわたります。
改正法は順次施行されますが、特に2025年10月1日から施行される「教育訓練休暇給付金」の創設は、企業にとって今後の労務管理や人材育成戦略を考えるうえでの重要なポイントとなります。
今回は、教育訓練休暇給付金について対応すべきポイントに焦点を当て、その具体的な内容を解説していきます。
雇用保険法改正の背景にある社会的な状況
今回の雇用保険法の改正は、日本の労働市場が直面するいくつかの重要な変化に対応するためのもので、その背景には少子高齢化の加速による労働力人口の減少や働き方の多様化、育児と仕事の両立支援の必要性の高まりといった要因が深く関わっています。
従来の雇用保険制度は、主に失業した労働者への経済的な支援と再就職の促進を目的としてきましたが、現在は労働者のキャリア形成をより積極的に支援することが求められており、経済的な変化の激しいなかで、企業が持続的に成長していくための環境整備なども課題とされています。
こうした社会的な状況を踏まえ、改正雇用保険法は失業者のセーフティネットとしての機能に加え、労働者の主体的な能力開発の支援や育児休業の取得促進、経済的支援の拡充といった、より幅広い視点から制度を見直すものとなっています。
企業は改正の趣旨を理解し、社会の変化に対応した柔軟な働き方や人材育成の仕組みを構築していかなければいけません。
そんな多岐にわたる改正のなかでも、2025年10月1日から施行される「教育訓練休暇給付金」の創設は、特に「人への投資の強化」という側面の強いものとなっています。
労働者が給付金を受けるための要件
教育訓練休暇給付金は、労働者がキャリアアップなどのために、休暇を取得して学習に専念することを国が経済的に支援するためのものです。
これにより、従業員のスキルアップを促し、企業の生産性向上や競争力強化につなげることを目的としています。
具体的には、要件を満たした従業員が、教育訓練を受けるための休暇を自発的に取得した場合に、基本手当(失業手当)に相当する給付金が国から支給されます。
定められた要件はいくつかありますが、対象となるのは、被保険者期間が5年以上で、休暇開始前の2年間に「みなし被保険者期間」が12カ月以上ある従業員に限られます。
みなし被保険者期間とは、被保険者期間に相当する期間のことで、休暇を開始する日を被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして計算されます。
対象となる従業員が、労働協約や就業規則などにより設けられた制度に基づき、自発的に30日以上の教育訓練休暇を取得した際に、失業手当と同額の支給が受けられます。
給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれかです。
また、給付の対象となる教育訓練は、厚生労働大臣や職業安定局長が指定する教育訓練および大学・高等専門学校・専修学校または各種学校が行う教育訓練に限られ、たとえば、趣味のための講座やカルチャーセンターで行われている教室などは対象外となります。
制度導入にあたり企業が行うべき環境の整備
教育訓練休暇給付金の創設は、企業にとって従業員のスキルアップの促進や人材の定着、企業競争力の強化などのメリットをもたらします。
従業員が主体的に能力開発に取り組むことを奨励することによって、専門性の高い人材育成につながりますし、学習意欲の高い従業員のキャリア形成を支援することは、エンゲージメントを高めることにもなるでしょう。
当然、スキルアップした従業員の増加は、企業の生産性向上やイノベーション創出を促進し、競争力の強化になります。
ただし、この教育訓練休暇給付金を利用するための環境を整備しないと、効果は限定的なものになってしまいます。
まず、企業側は社内において、教育訓練休暇に関する制度をきちんと設計する必要があります。
就業規則や関連規程を見直し、必要に応じて整備を進めていきましょう。
有給・無給、取得可能な日数、申し出の期限、申請手続きなどを明確化することで、使いやすい制度にしていかなければいけません。
また、従業員が安心して教育訓練に専念できるよう、業務の調整や代替要員の確保など、両立支援策も検討する必要があります。
教育訓練休暇給付金は、原則として、教育訓練休暇の期間や目標、内容などについて合意を得たうえで、企業は教育訓練休暇の取得を希望した従業員の賃金支払状況や休暇期間などを、管轄のハローワークに届け出る必要があります。
さらに、該当の従業員を事業主が解雇予定でないことを明記した証明書類も用意しなければいけません。
このように、教育訓練休暇給付金の利用は、労使の協力関係が必要不可欠となります。
従業員の学び直しが組織の成長につながるということをよく理解して、環境の整備を進めていきましょう。
2025.07.17【人的資源】個人のスマホを業務に使用する『BYOD』のメリット・デメリット
今やスマートフォン(以下スマホ)は人々の生活に必要不可欠なツールとなりました。
近年、ビジネスの現場において、従業員が個人で所有するスマホを業務に活用する「BYOD(Bring Your Own Device)」という取り組みが注目を集めています。
BYODは、従業員が慣れた自分のスマホを業務に利用できるため、スムーズな業務遂行や生産性の向上につながる一方で、セキュリティ対策や管理体制の構築など、企業が考慮すべき点も少なくありません。
導入を考えている企業に向けて、BYODのメリットとデメリットを中心に解説します。
スマホの普及に伴い注目を集めるBYOD
スマホの個人保有数は年々増加の一途をたどり、2024年には携帯電話所有者の内、スマホを所有している人の割合が97%に達したというデータがあります。
また、スマホはビジネスパーソンにとっても必須のツールです。
連絡手段としてはもちろん、情報収集、スケジュール管理、アプリケーションの利用など、多岐にわたる業務をスマホ1台で対応する人も数多くいます。
こうした背景もあり、従業員が個人で所有しているスマホを業務に活用する「BYOD」という取り組みが注目を集めています。
実は以前から、アメリカの企業などで導入されてきたBYODですが、本格的に注目を集めるようになったのはスマホの高性能化と普及が進んだ最近です。
かつては、会社から支給されるモバイルツールといえば、携帯電話やPHSが主流でしたが、スマホの登場により、個人の所有するスマホが業務に必要な機能を十分に満たすようになりました。
日本においても、働き方改革やコスト削減といった企業の課題解決策の一つとして、BYODへの関心が高まっており、特に柔軟な働き方やリモートワークを推進する企業を中心に、BYODの導入が進みつつあります。
そんなBYODの最大のメリットは、業務効率の向上です。
従業員は普段から使い慣れた自分のスマホを利用できるため、新しいデバイスの操作を覚える手間が省け、スムーズに業務に取り組むことができます。
個人の好みに合わせたカスタマイズが可能なので、作業効率の向上にもつながるでしょう。
また、業務に個人のスマホを使用するため、企業は端末の購入費用や維持費用を削減できるという利点もあります。
通常は社用のスマホを従業員の数だけ用意しなければならず、それだけでかなりのコストがかかってしまいます。
従業員にとっても、社用と私用の2台持ちを避けることができますし、自分好みのデバイスを業務に利用できることは、モチベーションアップになり、仕事の満足度向上も期待できます。
セキュリティリスクと導入の際の注意点
さまざまなメリットのあるBYODですが、一方で、導入に慎重な企業も依然として多く存在しています。
BYODを導入している企業は、2018年時点で10%ほどという総務省の調査結果もあります。
BYODの導入において、最も懸念されるのがセキュリティリスクです。
個人所有のスマホは、業務用のセキュリティ対策が十分に施されていない場合があり、マルウェア感染や情報漏洩のリスクも低くはありません。
また、紛失や盗難のリスクも考慮する必要があります。
次に、管理の複雑化への懸念です。
機種やOS、バージョンが異なる多種多様なデバイスを管理する必要があるため、IT部門の負担が増加する可能性があります。
セキュリティポリシーの適用やソフトウェアのアップデートなどを個々のデバイスに対して行う必要があり、管理が煩雑になってしまいます。
また、古い機種を使用している従業員と最新機種を使用している従業員との間で、業務効率に差が生じる可能性もありますし、公私の線引きがあいまいになることもリスクといえます。
こうしたデメリットを理解したうえで、導入には慎重な検討と周到な準備が必要です。
まず、BYODには明確なポリシーとガイドラインの策定が不可欠です。
利用可能なデバイスの範囲、セキュリティ要件、業務利用と私的利用の区分、紛失・盗難時の対応などを明確に定めましょう。
適切なセキュリティ対策の導入も必要になります。
MDM(Mobile Device Management)などの管理ツールを導入し、デバイスの一元管理、セキュリティポリシーの適用、リモートロックやワイプなどの機能実装を行うことが重要です。
また、従業員に対するセキュリティ教育を徹底し、セキュリティ意識の向上を図る必要があります。
さらに、サポート体制の整備や、費用負担に関するルールの明確化、従業員への周知なども欠かせません。
BYODは、適切に導入することで、コスト削減や業務効率化、従業員の満足度向上につながる可能性がありますが、セキュリティリスクなどの課題が多いことも理解しておきましょう。
2025.07.03【労働法】派遣契約を解除する前に派遣先企業がやるべきこと
派遣契約の終了は、当事者である派遣労働者だけでなく、派遣先企業にとっても重要な局面を迎えることを意味します。
これらのルールを守らずに派遣契約を解除してしまうと、派遣元企業や派遣労働者との間でトラブルが生じたり、法的責任を問われたりするおそれがあります。
派遣契約の解除を適切に行うために、派遣先企業が理解しておくべき基本を解説します。
派遣元企業と派遣先企業と派遣労働者の関係
「派遣労働」とは、人材派遣会社などの派遣元企業が雇用している労働者を、派遣先企業の指揮命令によって労働させる働き方です。
この形態において、雇用契約は派遣元企業と派遣労働者の間で結ばれますが、実際の業務指示や日常的な労務管理は派遣先企業が行うという、三者による関係が成立します。
たとえば、派遣労働者への給与の支払いや社会保険の手続きなどは雇用契約を結んでいる派遣元企業が行い、現場での業務指示や労務管理などは派遣先企業が行います。
派遣労働は特殊な労働形態であるため、派遣労働者の権利保護や、派遣先・派遣元企業の責任を明確にするため「労働者派遣法」という法律が定められています。
1986年に施行された労働者派遣法は、何度かの改正を経て、派遣契約の内容や派遣期間の制限、派遣先企業の義務などを細かく規定しており、派遣に関わるすべての企業はこれらの遵守が求められます。
派遣契約は、この労働者派遣法に基づいて結ばれるものであり、法律に違反する内容の契約は無効とされます。
そして、派遣先企業が特に注意すべきなのが、派遣契約を終了させるタイミングです。
人材派遣契約の終了には、「契約期間満了」と「契約の途中解除」の二つのケースがあります。
契約期間満了による派遣契約の終了
契約期間満了は、あらかじめ定められた派遣契約の期間が終了することで契約が終了するケースを指します。
派遣契約は一般的に、3カ月や6カ月単位など一定の期間を定めて締結されます。
派遣元企業は、通常、契約終了の1カ月前程度を目安に、派遣先企業および派遣労働者に契約更新の意向を確認します。
両者が更新を希望すれば契約は継続され、いずれかが希望しないのであれば、満了をもって契約は終了となります。
ただし、契約が更新された場合でも、労働者派遣法には、「個人単位の派遣期間制限」が設けられています。
このルールは、同一の派遣労働者が課や係などの同一の組織単位で就業できる期間を原則3年に制限するもので、雇用の安定や直接雇用への転換を促進する狙いがあります。
派遣先企業が3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れるには、派遣元企業による無期雇用化、または、派遣先企業による直接雇用などを検討する必要があります。
契約の途中解除による派遣契約の終了
契約期間満了に対して、契約の途中解除は、契約期間中になんらかの理由により契約を終了させるケースです。
これには、派遣先企業や派遣元企業の都合による解除、または派遣労働者の都合による退職などが含まれます。
契約の解除は予期せぬ事態によって発生することが多く、特に派遣先企業には慎重な対応が求められます。
原則として、派遣先企業は派遣契約を途中で解除することができないとされています。
なぜなら、労働者派遣法では、派遣先の都合による一方的な契約解除は、派遣労働者の雇用の安定を損なうおそれがあるとして、厳しく制限されているからです。
それでも、契約を解除する場合には、正当な理由が必要になります。
経営状況の急激な悪化や工場の閉鎖による派遣業務の消滅など、やむを得ない理由がある場合に限り、契約解除が認められることがあります。
単なる業務量の減少や、派遣社員の能力不足といった理由だけでは、不当な契約解除と判断される可能性が高くなります。
契約を途中解除する際には、原則として30日前までに派遣元企業へ通知すると共に、理由についても丁寧に説明し、承諾を得る必要があります。
派遣元企業は、派遣労働者の雇用主としての責任を負っているため、契約解除によって派遣社員が不利益を被らないよう、再就職先の確保などの措置を講じる必要があります。
派遣先企業はこうした派遣元企業の対応に協力しなければいけませんし、派遣労働者への配慮も必要になります。
また、派遣社員本人にもできるだけ早く通知し、理由を説明して理解を得ることが重要です。
突然の通知は、派遣労働者に大きな不安を与えるため、誠意をもって対応することが求められます。
さらに、労働者派遣法では、派遣元企業が派遣労働者を休業させ、休業手当を支払った場合には、派遣先企業は派遣元に対して、その相当額を支払う義務があると定められています。
また、派遣契約の解除により派遣労働者が損害を受けた場合、派遣先企業が損害賠償責任を負う可能性もあります。
不当な契約解除と判断された場合には、その責任はより重大となるため、法的観点からも慎重な判断が必要です。
派遣契約の解除は、派遣労働者のキャリアや派遣元企業の経営、そして派遣先企業の今後の人材戦略に大きな影響を及ぼします。
三者間で適切なコミュニケーションを図り、常に丁寧かつ誠意ある対応を行うことが、円満な契約終了のためのポイントとなります。
2025.07.03【人的資源】休職との違いは?『キャリアブレイク』経験者に熱視線!
働き方の多様化が進むなかで、日本でも「キャリアブレイク」という考え方が広まってきました。
キャリアブレイクとは、労働者が仕事から一時的に離れ、自身のキャリアや人生について深く考える期間を指します。
近年では、欧米を中心にキャリアブレイクを前向きにとらえる動きがあり、日本でもキャリアブレイク経験者の採用を積極的に行なっている企業があります。
今回は、企業の採用担当者に向けて、キャリアブレイクの具体的な中身や経験者が注目される理由などを説明します。
企業キャリアブレイクの重要性が注目される理由
キャリアブレイクの目的は、労働者が日々の業務から離れ、自己の内面と向き合い、本当にやりたいことや目指す方向性を再確認することにあります。
また、これまで培ってきたスキルや経験を振り返りながら、今後のキャリアプランを戦略的に練り直すことも含まれます。期間は数週間から数カ月、あるいは1年以上に及ぶことも少なくありません。
従来の働き方において、キャリアは直線的に積み重ねていくものと考えられがちでしたが、変化の激しい社会情勢や個人の価値観の多様化に伴い、今はキャリアの途中で意図的に立ち止まり、方向転換や再構築を図るという考え方が広まりつつあります。
キャリアブレイクは、決してキャリアの停滞ではなく、むしろより充実した自分らしいキャリアを築くための積極的な行動と位置づけられます。
キャリアブレイクは、リカレント教育やワークライフバランスなどが注目されている現代だからこそ、より重要性が高まっています。
終身雇用制度の崩壊や雇用の流動化が進むなかで、労働者は一人ひとりが主体的に学び直し、自身のキャリアを形成していく必要があります。
そのため、労働者は企業に依存するのではなく、自分のスキルや経験を磨き、市場価値を高めていかなければいけません。
また、長時間労働や過度なストレスを避け、自分自身の時間や価値観を大切にしたいというニーズが高まるなかで、心身のリフレッシュを図り、新たな気持ちで仕事に向き合うための期間も必要です。
さらに、グローバル化の波も無視できません。
海外では、キャリアブレイクは一般的な概念として浸透しており、多くの人々が積極的に活用しています。
日本においても国際的な競争力を高めるためには、多様な経験や価値観を持つ人材の育成や活用が不可欠であり、キャリアブレイク経験者は、その一翼を担う存在として期待されています。
ただし、海外におけるキャリアブレイクは、在職中に企業が制度として設けたり、個人が自発的に申し出て一定期間休職したりするケースが多いのに対し、日本では一旦退職して、期間を空けて転職活動を行うというケースがよく見られます。
このような状況から一部の企業では、社員のキャリア自律を支援する観点から退職ではなく、一時的な休職として業務から離れる「キャリアブレイク制度」を導入する動きも出てきています。
キャリアブレイク経験者採用時のポイント
日本でもキャリアブレイクを経験した人材の持つ可能性に注目し、積極的に採用しようとする企業が増加しています。
これらの企業は、労働者のキャリアブレイクを通して得られた主体性や多様な視点、適応能力、そして何よりも成長意欲の高さを評価しています。キャリアブレイク中に、異文化に触れたり、新しい分野を学んだり、社会貢献活動に参加したりと、多様な経験を積んだ人材は、従来の組織にはない新たな視点や発想をもたらしてくれる可能性があります。
また、みずからの意思でキャリアを中断し、将来について深く考え、行動してきた経験は、高い主体性と自律性の礎となります。
キャリアブレイク経験者は、みずから課題を発見し、解決に向けて積極的に動く人材の可能性が高いといえます。
さらに、キャリアブレイクという大きな変化を経験し、乗り越えてきた人材は、変化への適応力や柔軟性が高い傾向にあります。
不確実性の高い現代において、環境の変化に対応できる人材は、組織にとって大きな強みとなります。
このようなキャリアブレイク経験者を採用する際は、なぜキャリアブレイクを選択したのか、その期間に何を経験し、何を得たのかを詳しくヒアリングしましょう。
単なる離職期間としてとらえるのではなく、その経験が応募者の成長にどのように影響しているのかを見極めることが重要です。
同時に、キャリアブレイクを経て、どのようなキャリアを描いているのか、自社でどのように活躍したいと考えているのかを具体的に確認する必要があります。
入社後のミスマッチを防ぐためにも、双方の考え方や価値観をすり合わせるようにしましょう。
キャリアブレイク経験者の採用は、従来の採用選考とは異なる視点を持つことが重要です。
たとえば、書類選考や面接だけではなく、グループディスカッション、ワークショップなど、多様な選考方法を取り入れることで、応募者の多面的な能力や適性を評価することができるでしょう。
2025.06.19【労働法】企業が『労働組合』と協力関係を築くメリット
近年、労働組合に加入する労働者の割合が減少傾向にあります。
しかし、労働組合は労働者の権利を守り、労働条件の維持・改善を求めるうえで重要な組織です。
労働組合法は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者が会社と対等な立場で交渉できるようにすることを目的としています。
企業としては、労働組合との関係を敵対的なものではなく、協力的なパートナーシップとしてとらえることで、多くのメリットが生まれます。
労働組合の基礎をおさらいしつつ、企業が労働組合と協力関係を築くことによる具体的な利点を解説します。
労働組合の基礎と企業が注意するべきこと
厚生労働省の調査によると、2024年6月30日時点で、労働組合に加入する労働者の割合(推定組織率)は16.1%と、前年(16.3%)から0.2ポイント低下し、過去最低を更新しました。
1980年代前半には30%台だった労働組合の組織率は、産業構造の変化や非正規雇用の増加などに伴い、減少し続けています。一方で、パートタイムで働く組合員は146万3,000人と、前年より5万3,000人(3.8%)増加し、過去最高となりました。
パートタイム労働者の全労働組合員数に占める割合は14.9%で、前年より0.6ポイント上昇しています。
このように、労働組合のかたちも時代に合わせて変化していると見られます。
労働者の権利を守る労働組合は、労働者が主体となって労働条件の維持・改善などを目的として組織する団体と定義されます。
労働組合の種類は主に3つに大別され、企業ごとに組織された労働組合を「企業別労働組合」、同じ産業の労働者が集まって組織された労働組合を「産業別労働組合」、個人加盟制でさまざまな業種の労働者が加入できる労働組合を「合同労働組合(ユニオン)」と呼びます。
日本の労働組合の多くは企業別労働組合で、特定の企業の正社員を対象にしています。
大企業では労働組合があることが多いものの、中小企業では組織率が低く、そもそも加入できる組合がないケースも少なくありません。
自社に労働組合が存在しないため、産業別労働組合や合同労働組合に加入する労働者もいます。
企業としては、こうした労働組合と賃金や労働時間などの労働条件について交渉を重ねることになります。
労働組合法では、労働組合との団体交渉に応じる義務や、労働組合の運営に対する不当な介入の禁止などが定められています。
これらの義務に違反した場合、不当労働行為として法的責任を問われる可能性があるので注意してください。
労使間のコミュニケーションにも重要
企業と労働組合は、労働条件について交渉するうえでは対等な立場です。
立場の違いから対立することもありますが、本来は敵対関係ではなく、協力関係を築くべきパートナーといえるでしょう。
労働組合は労働者の意見を集約し、会社に伝える役割を担っており、会社の健全な発展に貢献する可能性を持っています。
では、企業にとって、労働組合と協力関係を築くことで、どのようなメリットが考えられるでしょうか。
一つに、労使間のコミュニケーションの円滑化があります。
労働組合との定期的な協議や交渉を通じて、労使間のコミュニケーションが円滑になれば、労働者の不満や要望を早期に把握し、問題が深刻化する前に適切な対応を取ることができます。
従業員が個人的に言い出しにくいことでも、労働組合を通してであれば意見を伝えやすくなりますし、その意見が会社に受け入れられることで、エンゲージメントが高まり、組織全体の活性化につながるでしょう。
厚生労働省の「令和元年(2019年)労使コミュニケーション調査の概況」によると、労働組合がある企業は、存在しない企業と比べて、労使関係が安定的に維持されていると回答する割合が高い傾向にありました。
労働組合の存在による労使間の円滑なコミュニケーションが、労働問題やトラブルの未然防止に寄与する結果となっています。
訴訟や労働争議などのリスクを回避できれば、企業にとって大きなメリットとなるでしょう。
また、労働組合との交渉を通じて、労働時間、賃金、安全衛生などの労働条件を改善することで、労働者のモチベーションや生産性を向上させることができます。
結果として、働きやすい職場環境になり、優秀な人材の確保や定着につながります。
さらに、労働組合との協力関係は、企業の社会的責任を果たすうえで重要な要素となります。
労働者の権利を尊重し、健全な労使関係を築くことで、企業の社会的信頼性を高めることにもなるでしょう。
労働組合は会社の健全な発展を支える重要なパートナーです。
協力関係を積極的に築き、労使間の信頼関係を構築することで、さまざまなメリットを享受できるようになります。
ただし、労働組合との関係構築は一朝一夕にできるものではありません。
根気強く、誠実な対応を続けることが重要です。
必要に応じて、専門家にも助言を求めるようにしましょう。
2025.06.19【人的資源】属人化の防止にも!『社内FAQ』を導入して活用する方法
特定の社員しかわからない業務や知識がある状態、いわゆる「業務の属人化」は、担当者が不在になると業務がストップしてしまったり、ノウハウが蓄積されず生産性が低下してしまったりするなど、企業にとって大きなリスクとなります。
そこで、属人化を防ぎ、仕事の効率化や生産性の向上を図る手段として導入したいのが、「社内FAQ」です。
社員の誰もが社内FAQにアクセスできるようにすることで、属人化の解消につなげることができます。
業務の標準化には欠かせない、社内FAQを導入する方法を解説します。
社内FAQの導入で得られる会社側のメリット
社内FAQとは、社員が日々の業務で抱える疑問や質問とその回答をまとめ、社内で共有するための情報システムです。
業務に関する知識やノウハウ、社内規定、各種手続きなど、社員が知りたい情報を網羅的に掲載することで、社員は必要な情報をいつでもどこでも簡単に入手できます。
最近では、社内FAQのシステムツールに、AIを搭載したものも増えてきました。
では、社内FAQを導入することで、会社側にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
主なメリットは業務の効率化と属人化の解消、そして、社員の自己成長の促進です。
疑問や質問が生じた際に、社員の誰もが社内FAQを検索することで迅速に解決策を見つけられるため、同僚や上司に時間を割いてもらう必要がなくなるため、両者の業務効率が向上します。
また、特定の社員しかわからない業務や知識をFAQに集約することで、担当者が不在の場合でも、他の社員がFAQを参照することで業務を遂行できるようになり、業務停止のリスクを軽減できます。
ノウハウが組織全体に共有されることで、担当者変更時の引継ぎもスムーズになるでしょう。
誰もが組織のノウハウを参照できるようにすることで、担当者による回答のばらつきを抑え、顧客対応の品質も向上します。
さらに、FAQを参照することで社員がみずから問題解決に取り組むようになり、自己解決能力も向上します。
新人教育や研修においても、FAQを活用することで効率的に知識を習得できるため、育成コストの削減にもなるといわれています。
FAQへの質問や回答を通じて、社員同士の相互理解が深まることになるため、組織のチームワークにもよい影響を与えます。
作成時の注意点と作成後に取り組むこと
多くのメリットのある社内FAQですが、作成する際には、まず目的と範囲を明確にする必要があります。
最初に、社内FAQで解決したい課題や対象範囲を具体的に定めることが重要です。
もし、課題や範囲を定めずにあいまいなままにしてしまうと、FAQが膨大になりながらも、肝心の答えが見つからないという事態を引き起こしかねません。
「どんな困りごとを、どう解決するか」を最初に具体的に絞り込むことで、必要な情報がしっかり網羅された役立つ社内FAQをつくることができます。
次に、社員からの質問、過去の問い合わせ履歴、業務マニュアルなど、あらゆる情報源からデータを収集する必要があります。
集めた情報を整理し、適切なカテゴリに分類することで、FAQの使いやすさを向上させます。
質問と回答を作成する際には、具体的かつわかりやすい記述を心がけましょう。
そして、社内FAQが完成したら、社員に周知することが大切です。
せっかくFAQを構築しても、社員がその存在を知らなければ利用されることはありません。
社内ポータルサイトやグループウェアなど、社員が日常的に使うツールを使って周知・公開することが大切です。
また、FAQは常に最新の情報に更新しておかなければいけません。
周知とあわせて、社員からのフィードバックを募りましょう。
フィードバックされた情報をもとに改善を重ねることで、より役立つ情報源となります。
社内FAQを導入するためのツールとしておすすめなのは、社内FAQに特化した専用のシステムツールです。
専用のシステムツールは、FAQ作成・管理の機能を持ち、効率的な運用が可能なため、多くの企業で採用されています。
一方で、導入後に活用できていない企業が多いこともわかっています。
社内FAQは前述した通り、常に改善が必要な情報システムです。
情報が古くなると、社員は社内FAQを信用しなくなり、利用率が低下してしまいます。
常に最新の情報に更新するような仕組みとあわせて、社内FAQを導入することが大切です。
また、社内FAQの利用を面倒に感じる社員の存在も想定されるため、利用促進のための施策も考えておきましょう。
社内FAQは、業務の効率化や属人化の解消、社員の自己解決能力向上など、企業にとって多くのメリットをもたらしますが、導入にあたっては、社員への周知と利用促進を徹底することが重要です。
2025.06.05【労働法】『就業規則』を変更するタイミングと法的な要件
就業規則は従業員が安心して働くための大切な規則です。
しかし、就業規則を最初に作成してから、何年もそのままだという企業も少なくありません。
就業規則は社会情勢や法令の改正、そして会社の成長や変化に伴い、常に最新の状態に保つ必要があります。
就業規則の変更は、適切なタイミングと法的な手続きを守って行うことが重要です。
もし、変更の際の手続きに不備があった場合、従業員との間で思わぬトラブルに発展するかもしれません。
就業規則を変更すべきタイミングや、具体的な変更の手順などについて、理解を深めておきましょう。
法改正や労働条件見直し時に変更
就業規則とは、会社が定める労働条件や服務規律に関するルールであり、従業員が働くうえでの基本的な決まり事を明確にしたものです。
労働時間や休憩、休日、賃金、服務規律、退職に関する事項など、多岐にわたる内容が記載されており、労働基準法では常時10人以上の従業員を使用する事業場に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務づけられています。
ただし、事業場ごとに作成するのが原則であるため、たとえば合計の従業員数が10人以上の会社でも、事業場で常時働く従業員が10人未満であれば、その事業場に関しては就業規則を作成する義務はありません。
この就業規則は、さまざまなタイミングで変更する必要があります。
その一つが、法令の改正が行われたタイミングです。
労働基準法をはじめとする労働関連の法令は、社会情勢の変化や働き方の多様化に対応するため、頻繁に改正されます。
たとえば、労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金に関する法改正など、企業の人事・労務管理に大きな影響を与える改正が行われることがあります。
このような法令の改正があった場合、既存の就業規則の内容が改正後の法令に適合しない可能性があります。
法令に反する内容の就業規則は無効となるため、速やかに就業規則を見直し、改正後の法令に合わせた内容に修正しなければいけません。
また、労働条件を見直したり、制度を新設したりする場合も、就業規則を変更しなければならないタイミングです。
勤務時間や休憩時間の変更、休日や休暇制度の見直しなどはもちろん、テレワーク制度や裁量労働制などの制度を導入する場合も、就業規則の変更が必要になることがあります。
なお、1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などについては、制度の適用にあたって就業規則に定めることが法的な要件になっているものもあります。
さらに、会社の組織再編や事業の拡大・縮小、新たな事業の開始など、企業の内部環境が大きく変化するタイミングでも、就業規則の見直しを行いましょう。
内部環境の変化に対して就業規則が古いままだと、実態とルールにずれが生じて、労使トラブルが起きやすくなりますし、労働基準監督署からの指導対象になるといったリスクがあります。
ほかにも、就業規則の不備や不明確な点が見つかったタイミングや、従業員の意見や要望があったタイミングなども、就業規則の変更を検討する必要があります。
変更した就業規則を無効にしないために
就業規則を変更するには、従業員代表への意見聴取を行い、変更する内容を明確にしてから、実際に変更した就業規則と、従業員代表の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働基準法では、就業規則の作成または変更を行う場合、使用者は事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(従業員代表)の意見を聴かなければならないと定められています。
従業員代表の意見聴取を行わないで変更した就業規則は無効になる可能性があるので、注意してください。
また、労働条件を変更する場合は、労働者の不利益にならない範囲で、かつ合理的なものでなければなりません。
賃金の引下げや手当の廃止など、労働者の不利益が大きい変更は無効と判断される可能性があります。
ただし、従業員にとって不利益となるかどうかは、変更の内容や必要性、変更後の労働条件の水準、従業員との交渉状況などを総合的に考慮して判断されます。
いずれにしても、就業規則の変更は従業員に寄り添った内容にしなければなりません。
変更した就業規則を労働基準監督署へ届け出た後は、従業員への周知を行いましょう。
周知の方法は、事業所内の見やすい場所に掲示する、書面を交付する、電子的な記録として保存し、従業員が容易にアクセスできるようにするなど、適切な方法で行う必要があります。
新しい就業規則が従業員に周知されていないと、その就業規則の効力が認められない場合があります。
就業規則を適切なタイミングで、法的な手続きに則って変更することは、労使間のトラブルを未然に防ぐことにもなります。
創業時に就業規則を作成したままであれば、あらためて見直し、必要に応じて変更を検討しましょう。
2025.06.05【人的資源】従業員のスキルアップも!『ハローワーク』を活用した人材育成法
従業員のスキルアップは、会社の効率化や企業価値の向上に欠かせません。
しかし、人材育成に割ける時間も費用も足りないという中小企業は多いのではないでしょうか。
そんな企業に向けて、ハローワークではさまざまな人材育成支援制度を提供しています。
ハローワークは、求職者への職業紹介だけでなく、企業の人材育成もサポートしており、これまでに多くの企業が支援を受けています。
ハローワークを活用した人材育成について、具体的な内容を紹介します。
中小企業在職者が対象のハローワークの支援
ハローワーク(公共職業安定所)は、雇用の安定と促進を目的とする公的な施設で、求職者と企業のマッチングや雇用保険の手続きだけではなく、職業訓練やスキルアップ支援なども行なっています。
企業側は、これらの支援制度をうまく活用することで、従業員の能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。
近年、終身雇用制度の崩壊や技術革新の加速により、企業は従業員の能力開発に力を入れる必要性が高まってきました。
今後は、どの産業においても、ますます労働力が不足する見通しとなっており、人材の確保と育成は企業の最優先課題の一つといわれています。
このような状況下で、ハローワークが提供する人材開発支援は、企業にとって非常に有益なものとなります。
人材育成に取り組む企業に向けたハローワークの支援策は目的別に分かれています。
たとえば、人材育成全般の基盤を整備したいのであれば、「キャリアコンサルティング」や「ジョブ・カード」などの導入に対して、助成金などの支援を受けることができます。
キャリアコンサルティングとは、国家資格を持つ専門家が労働者のキャリアプランや能力開発に関する助言や指導を行う取り組みのことです。
ジョブ・カードとは、職業経験・スキル・資格・キャリアプランなどを整理して、見える化したツールのことで、従業員のキャリア形成上の課題の把握や、能力開発の推進などに利用されます。
従業員の育成を外部の専門家に任せるケース
助成金を受けずに従業員を育成するのであれば、「ハロートレーニング」「認定職業訓練」「若年技能者人材育成支援等事業(ものづくりマイスター)」といった制度の利用を検討しましょう。
ハロートレーニングとは、ハローワークが提供する育成制度の一つで、求職者を対象としたものだけでなく、主に中小企業に在職中の従業員を対象としたコースもあります。
ハロートレーニングのなかでも、在職中の従業員向けの「在職者訓練」は、業務に必要な専門知識や技能・技術の向上を図ることが目的となっています。
「ものづくり」の分野を中心に、設計・開発、加工・組立、工事・施工、設備保全などの実習を中心とした訓練が全国の「ポリテクセンター(職業能力開発促進センター)」などで実施されます。
在職者向けのハロートレーニングは、2~5日間と比較的短期間であることが特徴で、企業が独自に研修を実施するよりも費用を抑えられる場合があり、専門的な知識・スキルを持った講師から指導を受けられるというメリットもあります。
また、ポリテクセンターだけではなく、都道府県知事の認定を受けた職業訓練施設でも在職者向けの訓練を実施しており、こちらは建築・土木関係、金属・機械加工関係、理美容関係などが主な訓練科となっています。
社外施設で訓練を受けるのではなく、講師の派遣を受けたいのであれば、「ものづくりマイスター」の利用も検討してみるとよいでしょう。
ものづくりマイスターとは、製造系職種やIT系職種で働く中小企業の若年技能者および工業高校の生徒などを対象に、派遣された熟練技能者が実技指導を行う制度です。
制度を利用することで、熟練技能者の知識・スキルを若手技能者に継承できるのはもちろん、OJTだけではむずかしい高度な技能を効率的に習得することができ、組織全体の技能水準も向上します。
特に中小企業においては、熟練技能者の高齢化による技能継承が課題となっており、ものづくりマイスターの活用は有効な手段となるでしょう。
ほかにも、ハローワークでは人材育成費用のサポートを受けることができる各種助成金制度や、自発的に訓練に取り組む従業員への教育訓練給付金制度などが用意されています。
人材育成は、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。
ハローワークの支援制度を積極的に活用し、従業員の能力を最大限に引き出すことで、組織全体のパフォーマンス向上につなげていきましょう。
2025.05.27 職場における熱中症対策の強化について 令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
2025.05.22【労働法】企業負担が軽減?『副業・兼業の通算ルール』見直しの狙い
近年、働き方の多様化が進み、副業や兼業を選択する人が増えてきました。
企業側も優秀な人材の確保や従業員のスキルアップを目的として、副業・兼業を容認するケースが増加傾向にあります。
しかし、副業・兼業が普及する一方で、本業と副業・兼業の労働時間や割増賃金などを通算して管理する「副業・兼業の通算ルール」が企業側の負担になっている場合もあります。
こうした状況を踏まえ、政府は「副業・兼業の通算ルール」の見直しを検討しています。
議論が進められているなか、見直しの背景や方向性、改正の時期などについて解説します。
副業・兼業を行う人が増えている?
法的な区別はありませんが、一般的に本業以外に収入を得るための仕事を「副業」といい、本業と並行して複数の仕事を持つことは「兼業」といわれています。
近年、本業以外に、この副業・兼業を持つ人が増加しています。
総務省が2022年に行なった約54万世帯を対象にした調査によれば、本業以外の副業を持つ人の数が305万人と、5年前よりも60万人ほど増えていることがわかりました。
本業を持つ人が副業・兼業を行う理由はさまざまですが、物価上昇や将来への不安から、収入を増やしたいと考える人が増えていることが一因としてあります。
また、スキルアップやキャリアの多様化も背景にあり、本業では得られないスキルや経験を積むことで、市場価値を高めたいと考える人も増えています。
さらに、インターネットやスマートフォンの普及により、時間や場所にとらわれない働き方が可能になったことも副業・兼業の増加を後押ししています。
一方、企業側にも、副業・兼業を容認することで、優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上につなげようとする動きが広がっています。
人材の流動化が進むなか、多様な働き方を認めることで、優秀な人材を確保することが可能になりました。
しかし、現行の労働基準法では、複数の企業で働く従業員の労働時間は合算されることになり、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた場合は企業が割増賃金を支払う、いわゆる「副業・兼業の通算ルール」が存在します。
このルールは、労働者の健康保護を目的としていますが、企業側にとっては、労働時間の管理が複雑になり、さらに法定労働時間を超えた分の割増賃金の支払いが必要になるという問題があります。
大企業のほか、中小企業にとっても、この「副業・兼業の通算ルール」が負担となっている可能性があります。
通算ルールにおける見直しのポイント
労働時間の管理について、企業は従業員の副業・兼業状況を把握して、正確に管理する必要があります。
しかし、副業・兼業状況は従業員の自己申告に頼らざるを得ず、従業員が自主的に副業・兼業を行なっている場合、企業がその状況を把握するのは容易ではありません。
そして、正しく状況を把握できなければ、適正な健康管理も行えません。
また、副業・兼業を行なっている従業員に対しては、割増賃金の計算も複雑です。
複数の企業で働く従業員の労働時間を通算する場合は、該当する従業員の労働時間を本業と副業とで1日ごとに細かく管理しなければならず、労働時間の配分や割増賃金の負担割合などで、他企業との調整が必要となる場合もあります。
このような理由から、副業・兼業の容認について、慎重な姿勢の企業もまだまだ存在します。
そこで、従業員の副業・兼業の機会が制限されないように、厚生労働省の労働政策審議会では、「副業・兼業の通算ルール」の見直しを踏まえた労働基準法改正に向けた議論を進めています。
たとえば、労働時間の通算方法の見直しについては、企業負担を軽減するために、勤怠管理の簡略化などが検討されています。
また、割増賃金の支払いについては、通算での労働時間の管理を廃止し、本業と副業・兼業先での労働時間は別個に管理するという案も浮上しています。
ただし、副業・兼業によって労働時間が過剰になることを防いで、労働者の健康を守るためにも、勤怠管理における労働時間の通算ルールは引き続き採用されると見られています。
通算ルールの見直しによって、企業側が期待できるのは、労働時間の管理にかかる負担の軽減です。
通算方法が簡素化されることはもちろん、割増賃金が通算ではなくなることで、計算や支払いにかかる手間やコストを削減できるでしょう。
こうした通算ルールの見直しは、企業側が副業・兼業を容認しやすくなるということでもあります。
負担が軽減されることで、企業は副業・兼業を積極的に推進しやすくなります。
通算ルールの見直しは、2026年に予定されている労働基準法の改正に向けた議論の一つです。
改正が正式に決まれば、企業側は副業・兼業に関する就業規則や労働時間の管理体制を見直す必要があるかもしれません。
今後の動向を注視しておきましょう。
2025.05.22【人的資源】『サイレントお祈り』はNG!?応募者への誠意ある対応とは?
近年、採用活動の場において、『サイレントお祈り』という言葉を耳にする機会が増えました。
サイレントお祈りとは、応募書類選考や面接後に、不採用者に対して企業側から連絡をしないことを指す俗語です。
採用活動の効率化などのために行われるサイレントお祈りですが、応募者に対して非常に失礼な行為であり、企業のイメージダウンにもつながりかねません。
サイレントお祈りの問題点などを含め、応募者への適切な対応について考えます。
サイレントお祈りは企業イメージの低下に
応募書類選考や面接の結果、不採用となった応募者に対して企業から送られる不採用通知メールのことを「お祈りメール」と呼びます。
メールの文末に「今後のご活躍をお祈り申し上げます」といった言葉が添えられることが多いため、いつからか求職者の間でこのように呼ばれるようになりました。
このお祈りメールから派生して、不採用者に対して企業側から連絡をしない「サイレントお祈り」という言葉も生まれました。
かつては、不採用者一人ひとりに不採用通知を送ることが一般的でしたが、近年では応募者数の増加や採用活動の効率化などを背景に、サイレントお祈りを選択する企業も出てきています。
近年、インターネットやスマートフォンなどの普及により、求職者は容易に多くの企業に応募できるようになりました。
そのため、特に人気の企業は大勢の応募者に対応する必要に迫られます。
さらに、採用活動にかかる時間やコストの削減を目的に、採用活動全体の効率化も考えなければいけません。
確かに、不採用者への連絡を省略することで、採用活動における負担を軽減することができます。
しかし、サイレントお祈りを行なっている企業に応募した人は、いつまでも合否の結果を知ることができず、連絡を待ち続けることになります。
就職活動や転職活動において、合否がわからなければ次の行動にも移れません。
したがって、サイレントお祈りは求職者にとって非常に不安な状況を生み出し、企業に対する不信感を抱かせる原因となります。
企業にとって、サイレントお祈りはデメリットのほうが多いといえます。
応募者に対する配慮が欠けていると受け取られ、企業イメージは悪化していきますし、SNSや口コミサイトでネガティブな評価が広がると、採用ブランディングにも悪影響を及ぼします。
近年はSNSなどで企業の採用活動に関する情報が拡散しやすくなっています。
サイレントお祈りを続けていると「応募したくない企業」として敬遠される可能性があり、人が集まらなくなる可能性があります。
優秀な人材ほど選考プロセスが丁寧な企業を選ぶため、結果的に採用の質が下がるリスクがあるでしょう。
応募者に対する誠意ある対応とは?
採用活動においては、まずできるだけ早く応募者に結果を知らせて、企業イメージを損なわないようにすることが重要です。
サイレントお祈りは避けるべき行為であり、合否にかかわらず、選考結果は必ず通知しましょう。
通知方法はメール、電話、郵送など、応募者が希望する方法でかまいません。
可能であれば、差し支えない範囲で不採用の理由に触れることも有効です。
応募者は不採用理由を知ることで、今後の就職・転職活動に役立てることができます。
採用活動の効率化を図るのであれば、テンプレートやフォーマットなどを活用して、手間をかけずに返信を行う仕組みを整えるのも方法の一つです。
企業側の負担を減らしつつ、応募者との良好な関係を維持する工夫を考えていくことが大切です。
企業によっては、応募者に対して誠意ある対応を行い、企業イメージを高めているケースもあります。
食品大手のカゴメ株式会社は、新卒採用活動において、エントリーシートや履歴書を提出したすべての学生に対し、自社製品のセットを贈る取り組みを15年以上前から続けています。
この取り組みはニュースや各メディアにも取り上げられ、話題になりました。
同社のような施策はむずかしくても、たとえば、採用活動の進捗状況や選考基準などを積極的に情報発信することで、応募者の不安を解消し、企業への信頼感を高めることはできます。
また、不採用の場合でも、丁寧なフィードバックを行うことで、企業の印象はよくなるでしょう。
応募者への誠意ある対応は、企業の信頼向上と採用力の強化につながり、優秀な人材の獲得にもつながります。
応募者の立場に立ち、信頼を獲得できるコミュニケーションを心がけることが重要です。
今一度、自社の応募者への対応を見直してみてはいかがでしょうか。
2025.05.08【労働法】違法になるケースも?『退職勧奨』を行う際の注意点
「退職勧奨」とは、会社が従業員に対して自主的な退職を促す行為のことを指します。
企業の人員削減や組織再編などに伴い、従業員に対して退職勧奨をしなければならないケースもあります。
しかし、手法を誤ると、従業員との間で深刻な労使トラブルに発展し、企業の信頼を大きく損なう可能性があります。
退職勧奨に関する法的な知識が曖昧なままだと、思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。
違法となる退職勧奨のケースや適切な手順について解説します。
違法になる可能性のある退職勧奨
企業が退職勧奨を行う理由はさまざまですが、近年は経営状況の悪化に伴い、人件費を削減する必要がある場合や組織体制を見直す場合に行われることが増えてきました。
こうした会社側の事情だけではなく、従業員の能力や適性が業務内容と合致しない場合などにも、退職勧奨が行われています。
退職勧奨は会社が従業員に対して退職を促す行為です。
あくまで会社は退職を促すのみにとどまり、退職するかどうかは従業員側の判断になります。
会社が一方的に労働契約を解除する「解雇」と似た部分もありますが、解雇は法的な要件が厳格に定められているのに対し、退職勧奨には法的な規制がありません。
しかし、法的な規制がないからといって、自由に退職勧奨を行なってよいわけではありません。
退職勧奨は従業員の自由な意思決定を尊重し、合意に基づいて進める必要があるため、強引な手法は認められていません。
もし、強引な手法で退職勧奨を進めると、労働基準法などに抵触する可能性があります。
過去の裁判例では、従業員が拒否しているにもかかわらず、長時間にわたって繰り返し退職勧奨を行ったケースや、怒鳴ったり机をたたいたりなどの威迫行為を行い従業員に退職を迫ったケースなどで、違法性が認められました。
また、執拗な退職勧奨や威迫行為だけではなく、脅迫的に退職を迫ったり、実際には拒むことができるのに、誤解させるような虚偽の説明で退職を促したりすることも、違法になることがあります。
さらに、退職に応じないからといって、業務を与えなかったり、嫌がらせをしたりといった不当な扱いをすることも禁じられています。
これらの行為は、従業員の自由な意思決定を妨げ、精神的な苦痛を与える可能性があるので、絶対に行わないようにしましょう。
もし、退職勧奨の違法性が認められると、会社側は従業員に対して損害賠償責任を負うことになりますし、退職自体が取り消されるため、退職してから現時点までの賃金も支払うことになります。
労働基準監督署からの指導・是正勧告を受ける可能性もあるので、注意しましょう。
従業員の合意を得られる退職勧奨の方法
違法な退職勧奨にならないためには、退職勧奨の理由を具体的に説明し、従業員の理解と納得を得ることが大切です。
従業員が退職について納得のいくまで検討できるよう、説明の時間と検討する期間を十分に確保することも必要です。
ただし、面談の時間は長時間にならないようにし、業務時間内に行うようにしましょう。
当然、従業員の意思を尊重し、強引な説得や強要は避けなければいけません。
退職を強制するような発言は避け、あくまで一つの提案として伝えることがポイントです。
もし、従業員が退職を拒否した場合も、執拗な説得は止めましょう。
また、場合によっては、両者合意のうえで面談での会話を録音しておきましょう。
退職勧奨の場では、後になって従業員側から「会社から強制された」「脅迫された」などの主張が出る可能性があります。
録音したデータがあれば、会話の内容を客観的に証明でき、不要なトラブルを防ぐことができるからです。
退職勧奨は本人の自由な意思に基づくことが前提です。
会社が無理に退職を強要したと判断されると、後から不当解雇として争われる可能性があります。
このように適法性を意識することも重要ですが、従業員と合意形成を図ることも大切です。
従業員側に合意を得やすい条件を提示することで、円満に退職してもらうことができます。
たとえば、退職金の増額や特別手当の支給など、金銭的なメリットを提示してみてはいかがでしょうか。
再就職先の紹介やキャリア相談の提供など、転職支援も効果的です。
条件面でも誠意をもって対応することで、合意を得られる可能性が高まります。
退職勧奨は企業にとってむずかしい課題の一つですが、従業員との信頼関係を維持しながら、適切に進めていくことで、双方が納得のいく結果になるはずです。
逆に、違法な退職勧奨は会社の信頼を大きく損なうだけでなく、法的なリスクも伴います。
退職勧奨を行う際は、従業員の立場に配慮した丁寧な対応を心がけるようにしましょう。
2025.05.08【人的資源】『ウェアラブルデバイス』を活用した従業員のストレス管理術
働き方の多様化や複雑化に伴い、従業員のストレス管理は企業にとって重要な課題となってきました。
ストレスは従業員の心身の健康を害するだけでなく、生産性の低下や離職率の増加など、企業の業績にも悪影響を及ぼしかねません。
そこで、注目を集めているのが『ウェアラブルデバイス』を活用したストレス管理です。
ウェアラブルデバイスとは、身に着けて使用する小型の情報端末のことで、心拍数や睡眠時間、活動量など、さまざまな生体データをリアルタイムで計測できます。
ストレス状況を客観的に把握することのできるウェアラブルデバイスの可能性を探ります。
ウェアラブルデバイスの種類と機能
ウェアラブルデバイスとは身に着けて使用する小型の情報端末の総称で、技術の進歩に伴い、さまざまな種類の端末が登場しています。
時計のように手首に装着するスマートウォッチはウェアラブルデバイスを代表する端末の一つで、時刻表示だけでなく、心拍数や睡眠時間、活動量などの計測機能などを搭載していることがほとんどです。
同じ時計型の端末でも、健康管理に特化したフィットネストラッカーとは区別されます。
また、メガネ型のウェアラブルデバイスであるスマートグラスは、視界に情報を表示することが可能で、スマートフォンなどの機器と連携して使用することもできます。
ほかにも、指輪型のスマートリングや靴型のスマートシューズなど、多種多様な種類のウェアラブルデバイスが販売されています。
種類にもよりますが、こうしたウェアラブルデバイスには心拍数や活動量のほか、体温、ストレスレベル、GPSなどの機能を備えているものも多く、日々の健康管理に役立てることができます。
このウェアラブルデバイスを従業員の健康管理に活用することで、従業員と企業の双方に大きなメリットをもたらします。
従業員は自身の健康状態を客観的に把握することで、ストレスや疲労の蓄積に気づきやすくなりますし、企業は従業員の健康状態を常に把握しながら適切にサポートすることで、ストレスや疲労による休職や離職を防止できます。
健康状態は集中力や業務パフォーマンスに大きく影響します。
個人の生活習慣の改善や健康増進は、企業における生産性の向上や、組織全体の活性化にもつながるでしょう。
多くの業界で使われるが導入には注意点も
実際に、ウェアラブルデバイスを従業員の健康管理に活用している企業が増えています。
たとえば、製造業では高温多湿な環境や危険な場所での作業における体調変化の早期発見、疲労度やストレスレベルのモニタリングによる作業負荷の調整や休憩時間の確保などに活用されています。
特に工場などでの夏場の作業は熱中症の危険があるため、ウェアラブルデバイスによる心拍数や体温などの監視は欠かせません。
物流・交通業界でも、運転中のドライバーの疲労度や眠気のモニタリングによる事故防止にウェアラブルデバイスを役立てています。
ドライバーの心拍数、脳波、まばたきなどを測定し、危険レベルの検知時にはアラートや振動で注意を喚起し、休憩行動を促します。
また、測定したデータを分析し、AIなどを活用して事故予防に役立てるという取り組みも行われています。
このような収集したデータをさらなる健康管理に活用していく動きは、ほかの分野でも見られます。
ただし、健康データは個人情報なので、取り扱いには細心の注意が必要です。
不正アクセスやデータ漏洩を防ぐためにも、強固なセキュリティ対策を講じなければいけません。
また、健康管理の名目で従業員の行動を過度に監視すると、逆にストレスや不満の原因になってしまうこともあります。
監視ではなく、従業員の健康をサポートするためのツールとしての位置づけであることを忘れないようにしましょう。
ウェアラブルデバイスの着用は、強制ではなく任意が基本になります。
従業員の自主性を尊重し、従業員の同意を得たうえで運用していくことが大切です。
さらに、ウェアラブルデバイスが導き出すデータは、医療機器ほどの精度はなく、ストレスや健康状態の測定値が誤差を含む可能性もあります。
あくまで参考値や目安として活用し、必要に応じて専門家の意見を取り入れることも考えておきましょう。
ウェアラブルデバイスを活用した従業員のストレス管理は、まだ始まったばかりの取り組みですが、その可能性は非常に大きいといえます。
今後は、さらに多くの企業がウェアラブルデバイスを取り入れ、従業員の健康管理やストレス管理に役立てていくことが予想されます。
より健やかに高い生産性で働ける環境づくりのためにも、ウェアラブルデバイスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
2025.04.17【労働法】『自爆営業』はパワハラ! 自社商品の購入強要に要注意
従業員が販売目標達成のために、自社の製品やサービスを自腹で購入することを「自爆営業」といいます。
自爆営業が行われる背景には、厳しいノルマが課され、その達成のために自腹で商品を購入せざるを得ない状況があるといわれています。
自爆営業の要因となる過大なノルマや上司からの叱責などによって、自死する人も出ていることから、厚生労働省は2024年11月に自爆営業をパワーハラスメントの一つであるとしました。
自爆営業に該当する事例や、自爆営業を続ける会社側のリスクなどについて解説します。
パワハラ防止法指針に自爆営業を明記する方針
利益を上げるために、一定のノルマを設定している企業は少なくありませんが、ノルマを達成できなかった際に、従業員が自腹で商品などを購入しなければならない状況に陥ることがあります。
ノルマ達成のために従業員が自腹で不要な商品を購入したり、不必要な契約を結んだりすることを「自爆営業」と呼びます。
内閣府が公開している資料では、保険契約数のノルマを達成するために、自腹で自動車保険に加入した中古車販売会社の社員の話や、自社の共済事業のノルマの達成のために不必要な共済を契約した農協職員の話など、自爆営業の事例が紹介されています。
特に高額な商品や季節食品などを扱っている会社では、自爆営業が深刻化する傾向にあるといわれています。
過去には、中古車販売会社の新入社員が半ば強制的に自社で販売している車を購入させられたケースや、セレクトショップの販売員が制服として売り場の商品を購入することになったケース、コンビニで働く外国人労働者が恵方巻きやクリスマスケーキを購入させられたケースなどがありました。
親を保険に加入させたり、親族名義でマンションを購入したりといった、従業員本人だけではなく、その家族にも影響が及ぶこともあり、自爆営業は労働者の大きな負担となっています。
これまでは実態が把握されておらず、違法性の判断基準も明確ではなかったことから、個別に自爆営業がパワハラだと認められるケースはあったものの、実質的には放置されてきました。
そのため、古くからの慣習として、自爆営業が黙認されていた業界や企業も少なくありません。
しかし、自爆営業は従業員に経済的な負担を強いるだけでなく、精神的な苦痛を与える可能性もあり、近年は自死する人も出ていることから、厚生労働省が自爆営業の防止に乗り出しました。
2024年には、「パワハラ防止法(労働施策総合推進法)」に基づくパワハラ防止法指針に、自爆営業がパワハラに該当する場合があると明記する方針が示されました。
自爆営業がパワハラになる3つの要素
では、どのような自爆営業がパワハラに該当するのでしょうか。
たとえば、ノルマや販売目標などが設定されていない会社で、従業員がみずからの意思で自社商品を購入する場合は、パワハラには当たりません。
パワハラになるのは、以下の3つの要素をすべて満たす場合とされています。
(1)優越的な関係を背景としている
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えている
(3)労働者の就業環境が害される
上司や会社が立場の弱い従業員に「ノルマ達成のために自分で商品を買うように」と、暗に強制するのは(1)に該当しますし、従業員がみずからの給与で自社の商品を買うのは(2)に該当します。
本来、販売ノルマの達成は企業の責任であり、従業員個人に負担させるのは合理的な業務範囲を超えているといえます。
従業員がみずからの給与で自社の商品を買う義務は一切ありません。
また、自爆営業によって従業員の経済的・精神的な負担が生じている場合は、(3)が当てはまります。
精神的なストレスが増して、仕事のモチベーションが低下する人や、追い込まれてうつ症状が出てしまう人もいるでしょう。
多くの自爆営業はこの3つの要素をすべて満たしており、パワハラに該当する可能性が高いといえます。
自爆営業がパワハラに認定される可能性が高まったことにより、企業はこれまで以上に自爆営業をさせないように気を配らなければいけません。
ノルマの設定が高すぎると、自爆営業が起きやすくなるため、まずは適切なノルマに設定し直す必要があります。
また、従業員に過度なプレッシャーをかける販売方法も見直し、チームで目標達成を目指すなど、協力体制を築いていくことも大切です。
さらに、管理職を対象に、研修などで自爆営業がパワハラに該当する可能性があることを認識してもらいましょう。
自爆営業は、優越的な関係を背景とした強制的な負担の押しつけであり、業務上の合理性を欠き、従業員の環境を著しく悪化させるパワハラの一種です。
従業員の信頼も失いますし、モチベーションの低下や離職につながる可能性もあります。
従業員に自爆営業をさせないことが、企業としての責務でもあります。
まずは、自社で自爆営業が起きていないか、社内調査などによって実情を確認しておきましょう。
2025.04.17【人的資源】企業が『ジョブシャドウイング』を実施するメリットは?
ジョブシャドウイングとは、学生や求職者が企業の社員に密着し、実際の仕事現場を見学したり、業務内容について説明を受けたりする取り組みのことを指します。
まるで影(shadow)のように社員に付き添うことからその名がついたジョブシャドウイングは、学生や求職者が実際の仕事に触れられるというだけではなく、企業側にもさまざまなメリットがあるといわれています。
近年、日本でも注目されつつあるジョブシャドウイングの中身について、解説します。
インターンシップと何が違うのか
学生や求職者が興味のある職種や企業で働く社員に同行し、その仕事内容や職場の雰囲気に触れることを「ジョブシャドウイング」と定義しています。
1996年にアメリカのマサチューセッツ州ボストン市で初めて行われ、同市の公立学校の生徒350名が参加しました。
以来、欧米ではジョブシャドウイングが一般的な職業体験プログラムとして広まり、主に学生向けのキャリア教育の一環として、今も広く活用されています。
ジョブシャドウイングの参加者は、訪問を受け入れている企業に赴き、一日の仕事の流れを見学したり、業務の説明を受けたり、時には簡単な作業を手伝ったりします。
こうした体験を通じて、参加者は仕事への理解を深め、将来的な進路の選択に役立てられます。
日本における学生の職場体験といえば「インターンシップ 」がよく知られていますが、インターンシップが数週間~数カ月間という長期間にわたって実施されるのに対し、ジョブシャドウイングは通常1日~数日程度の短期間で行われます。
また、実際に業務を担当するインターンシップに比べ、ジョブシャドウイングは社員の仕事を見学したり説明を受けたりすることが中心となり、実際に仕事に関わることはありません。
欧米では、インターンシップの前段階としてジョブシャドウイングを設けている企業も多く、まずは参加者の適性や関心を確認し、インターンシップのミスマッチを防ぐためにジョブシャドウイングが実施されることもあります。
企業側のメリットと実施する際の注意点
学生や求職者にとっては、進路選択の参考や情報収集、学習意欲の向上などに役立つジョブシャドウイングですが、企業にとっては、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まずは、企業の魅力を対外的にアピールできるというメリットがあります。
ジョブシャドウイングは学生や求職者に対して、自社の社風や仕事内容、社員の魅力を直接アピールする絶好の機会です。
実際に仕事現場を見学してもらうことで、企業の雰囲気や働く人々の様子を肌で感じてもらえるでしょう。
また、ジョブシャドウイングを通じて、学生や求職者の適性や興味・関心を把握できます。
これにより、採用選考のミスマッチを減らし、より自社に合った人材を採用することが可能です。
さらに、既存の社員にとっても、ジョブシャドウイングは成長するための絶好の機会になります。
自分の仕事内容を説明したり、学生や求職者からの質問に答えたりすることで、自身の業務に対する理解を深め、スキルアップにつなげられるでしょう。
こうした採用活動の効率化や人材育成の促進などのほかに、ジョブシャドウイングは学生や求職者のキャリア形成を支援する社会貢献としての側面もあります。
ジョブシャドウイングに取り組むことで、社会からの信頼を得られ、企業イメージや認知度の向上にもなります。
このように、さまざまなメリットのあるジョブシャドウイングですが、無計画なまま始めても成功しません。
まずは、ジョブシャドウイングの内容や計画、スケジュールや参加者への説明資料などを事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
また、社員が快く参加者を受け入れられるような雰囲気づくりや、質問しやすい環境を整えることも重要です。
実際のジョブシャドウイングでは、参加者からの疑問や質問には、丁寧に答えるように心がけましょう。
さらに、ジョブシャドウイングの終了後には、参加者からの反応や感想をフィードバックしてもらうことで、改善点を見つけられるため、よりよいものにブラッシュアップできます。
ジョブシャドウイングは実施する目的を明確にし、その目的に合ったプログラム内容にすることが成功の秘訣です。
自社でジョブシャドウイングを実施する場合には、まず、どのような制度設計になるのか考えてみるところから始めてみましょう。
2025.05.吉日 ホームページをリニューアルいたしました!!

ホームページをリニューアルいたしました。
しばらく編集中の箇所がございますが、ご容赦の程何卒よろしくお願い申し上げます。
事務所案内
| 会社名 | 志水社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 志水 美和子 |
| 所在地 | 〒503-0015 岐阜県大垣市林町2-61-2 ME大垣ビル1F |
| 電話番号 | 0584-71-6870 |
| 営業時間 | 09:00~17:00 (土日祝・年末年始休業) |
お問合せはこちらまで
お電話でのご相談・お問合せは、以下の電話番号までご連絡ください。
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。